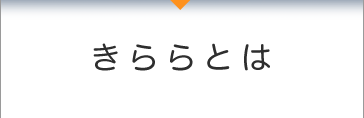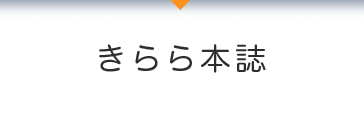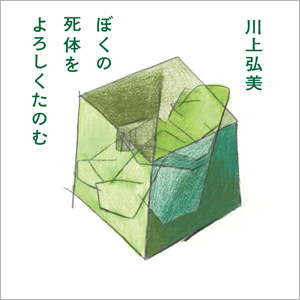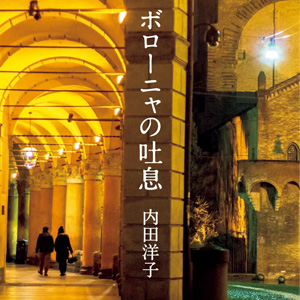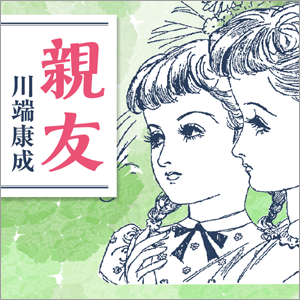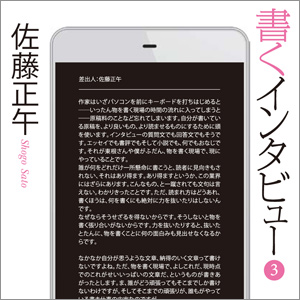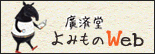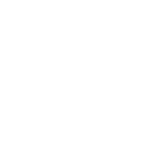| �z�[�� > �����ʐM > 2014�N |

|
|||||||
2014�N12���� �y127�z�@�͌�̖��l�펵�ԏ�����l�ǁB�e�l�̎������ԂW���Ԃ̂����A���Ղ��璧��҂͖̉�Ջ�i���P����22���A��R�T�����l���P����32���ƁA���Ɏ��Ԃ�v�����B�g�[�^���Q�������āA�r���Q�H���Ƃ�Ȃ���s������̂����A�I�ǎ��ɂ́A���ꂼ��̎������ԂP�A�Q�����x�ɂȂ�A�Ō�̕��́A������b�ǂ݂̏�ԂɂȂ����B�����A�͌�̂��Ƃ͑S���킩��Ȃ����A�Ȃ̂ɈȑO����͌�⏫���̍ō���̐킢���L���ɖڂ��s���Ƃ����������Țn�Ȃ�����̂����A����̒��l��郌�|�[�g��ǂ�ł��āA�ǂ����Ď䂩��Ă��܂��̂��A�����킩�����悤�ȋC�������B �@�����ʂ�l�X�Ȑ킢�̋ǖʂ��o�āA���A�����ɂ����l�̊��m�ɂƂ��āA���̔]���ł͂��̂��������ʂ̃V�~�����[�V������A���܂łɂȂ��A����̓ǂ݂�e�Ղɍs�킹�Ȃ��悤�ȐV������������ƂɑS���͂��X�����Ă��锤���B�������A����������Ƃ��A����̈�肪�u����邲�ƂɁA�ꍇ�ɂ���Ă͔��������Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ��B����ȕ��ɍl���Ă����ƁA���㌈��ł���A�Q�����Ƃ�������Ȉ�ǂւ̎��Ԃ��v����Ă���悤�ɂ݂��閼�l�탌�x���ł��A�������ԂW���ԂƂ����̂��ʂ����đÓ��Ȏ��ԂȂ̂��A�f�l�Ȃ������X�������Ȃ��Ă���B �@�͌�Ə����̔]���^���̂悤�Ȃ��̂��ꏊ�ɒu���čl����̂́A�������\�Ȃ悤�ȋC�����邪�A�����̎��M��������A������x���ɂȂ�ꏊ�ɗ����Ԃ��ď�����������A���ꂱ�����̈ꕶ�i�����o���̈ꕶ�ł��悢�j�ɁA�ƂĂ��Ȃ����Ԃ�v�����肷��ꍇ������B���悤�ɁA�������l�����肵�Ă��鎞�ԂƂ������̂́A�Z�\�i�@�ň��Ղɋ���Ă��܂����Ƃ�������̂ł���A����Ӗ��Ŏ��ԂƂ������̂��玩�R�ł��邱�Ƃ��K�R�̂��̂̂悤�Ɏv����B���ہA������ǂޑ��ɂ��A���R�A�����Ɏ��Ԃ̐���͂Ȃ��A�����낤���A�Z���낤���A�ǂꂾ�����Ԃ������Ă��悢���A�Ȃ�����A����ł��ǂ�ŁA�����Ȃ�Ɍ��������Ă����Ă��悢�̂ł���B�͌�̏ꍇ�A�ǂɓ�l��v���A���[��������ď��߂Đ��藧���̂ł���B�������Ԃ�݂��邱�Ƃ��ܘ_���[���Ƃ��Č��R�Ƃ��Ă���A�Ƃ�����������Ƃ������A�Ȃɂ���肫��Ȃ��A�s���Ȃ悤�Ȋ�����A�^��������Տ�ōs���Ă���l�ɑ��Ċ����Ă��܂��B �i II �j 2014�N11���� �y126�z�@�����h���S���Y�̓���E�R�{����49�Ō��𓊎�̍ŔN����������̋L�^���X�V�������Ƃ͋L���ɐV�����B�v���싅�I��Ƃ��āA��������ō���ł���A�����̑��q����̑I�肽���Ɠ��X�����Â��Ă���B�����܂ł̃x�e�����ɂȂ��Ă����A���܂�B��Ƃ����镐��ł��鋅�̃L���̐��x��ۂ��߁A�����t�H�[���̏C���ɖ������閈�����Ƃ����B����A�����̌^�i�X�^�C���j�Ƃ����Ă��悢�͂��́A�����t�H�[�����X�g�C�b�N�ɒ������Â���f�����e���r�Ō����̂����A�y���V���b�N�����B�ӂ��ɍl����ƁA���N�A������ƂɎ��g�ݑ����邤���ɁA���̂��ƌ^�̂悤�Ȃ��̂��o���オ��A����͔N�ւ����܂�Ă����悤�Ɋm�łƂ������̂Ƃ��Č���������Ă����悤�Ɏv���̂����A�싅�I��̏ꍇ�́A�܂������قȂ�悤���B�t�ɁA�ɉ����āA�Ӑ}�I�Ƀt�H�[�����������ς�����A���s��������X�ƌJ��Ԃ��Ȃ���łȂ��ƁA�v���̐��E�ł͂Ƃ��Ă�����Ă����Ȃ��̂��Ƃ����B����́A���X�ׂ̍��ȏ�Ԃ̍��ك��x���ł��N�����Ă��܂��A���Ƀf���P�[�g�Ȃ��̂̂悤���B �@�������Ȃ���A����́A�l�Ԃ�����Ă���̂�����A����Ӗ��A������O�̂��Ƃ̂悤�ȋC������ł͂���B��Ƃ̕��X�ɘb���Ă��Ă��A�����͒��q�������Č��e���͂��ǂ�Ȃ������Ƃ��A���̋t�Ɍ��e���i�A�Ƃ������b���悭���ɂ���B�܂�Ƃ���A���S���A�ꍇ�ɂ���Ă͐疇����悤�Ȍ��e�́A���R����ŏ�������̂ł͂Ȃ����A���X�̔���ȍD�s���̔g�������������Đ��ɐ��܂�o�Ă�����̂��Ƃ������Ƃɉ��߂ċC�t�������B��i�S�̂ŁA�ЂƂ̂��̂Ƃ��ēǎ҂̑O�Ƀ|���ƒ���邾���ɁA�ꌩ���̂悤�Ȃ��̂Ƃ��Ďv��ꂪ�������A�����琄�Ȃ��d�˂čŏI�I�Ɋ����`�ɂ�����ɂ��Ă��A���̍�Ǝ��̂��A��Ɉ��ł��葱����͂��̂��̂Ƃ��������A�ǂ��܂ł���������r���ł��Ȃ��A���̔w�i�ɂ����ȏ�����̎������ӏA�C�����̑��������ď��߂ďo���オ��u���ȃ��m�v�Ȃ̂��Ƃ������Ƃ��o����B����Ȃ̂ɁA�������Ĉ�x�o���オ���Ă��܂����u��i�v�͂���ȏ�ł��ȉ��ł��Ȃ��A����̕��䗠�̗l�X�Ȃǂ܂������C�z����Y���Ă��Ȃ������肷�邩��A�Ȃ��̂��ƕs�v�c�ł���B�Ƃ������A����ȕ��ɁA��Ƒ��̗l�X�ȑn��ߒ����܂����������Ă��Ȃ����̂����A�v���t�F�b�V���i���Ȃ��̂Ƃ�������B �i II �j 2014�N10���� �y125�z�@�ŏ��ɒf���Ă������A�������e�́A���S�ȃm���P�b�̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂ŁA���̓_�A�ǂ����������������������B �@���āB �@�ҏW�҂ɂƂ��āA�����ꂵ�������肷��u�Ԃ��Ăǂ�ȂƂ��Ȃ낤�H �@�ӂ���܂�l�����肵�Ȃ����A����Ȏ���������܂����������ȂǓǂ�ł��Ȃ��Ⴂ����̐l�ɐu����āA�v�킸���Ƃɂ܂��Ă��܂����B �@�S�����Ă���{�����ꂽ��A����Ȃ��Ă��A�����������{���ł�����A����̍�Ƃ���ƃQ����ł��Ƃ�ł����������Ă�����A�{���o�Ă����Ԃ�o���Ă���A���̖{�A�悩�����ł���A�Ǝv��ʐl���猾��ꂽ��A�ƂĂ��Ȃ��������Ԃ��������āA����ƌ��{���o���オ������ɁA���̖{��O�ɒ��҂Ƃ����₩�ȑł��グ��������B �@�������ɁA���̂�������A���Ȗ����X���X����������Ȃ��u���[�A�ҏW����ĂĂ悩�����v�Ƃ��������ɖ������Ă���悤�Ɏv���B �@�v����������Ă݂č��X�Ȃ���Ɏv�����̂����A�����������Ƃŏ[�������v�������ł���A����Ӗ��K���ȁA����������łȂ��ƁA�����������疱�܂�Ȃ��d���Ȃ̂�������Ȃ��B �@���Ȃ��Ƃ��A�����͊ԈႢ�Ȃ��������B�ق��̓��Ǝ҂ɖʂƌ������ĕ��������Ƃ͂Ȃ����A�����A���������C���Ƃ͂������ꂽ�A����탋�[�e�B���ȁu�d���v�Ɗ�����ĕҏW�����𑱂��Ă���l������Ƃ�����A����͂ƂĂ��s�K�Ȃ��Ƃł���A�t�ɁA�悭����ȕ��ɂ��Ďd�����ł�����̂��Ɗ��S���Ă��܂��͂����B �@����Ȃ��Ƃ������Ă���ƁA���������ȁA�Â����ꂽ���Ƃ����܂ł��������Ă��鈢�����Ǝv���������邩������Ȃ����A���̂��炢�A����Ӗ��A�������ꂵ���d���ȂƎv���A���̕��|�̕ҏW�҂Ƃ������̂́B �@���āA�b���v��������E�����Ă��܂������A�`���̏����̕ҏW������Ă��āA�������������ʔ����̂��A�I�Ȗ₢�ւ́A�����_�ł̎����̂Ԃ�������̑��ʂ̃J�^���V�X�̏u�Ԃ́A���������������ăf�r���[������Ƃ��A�e�Ѝs�đ҂قǂ̂��ƂɂȂ�A10�N�ԏ����������ߖڂ̍�i���A�P�N�ȏ�قڂ���ɖv����������A�P�O�O�O�������̏㉺���Ƃ��Ċ��s�ł��邱�Ƃ�u���Ăق��ɂȂ��悤�Ɏv���B �@����Ȗ{���A����10�����ɔ��������B �i II �j 2014�N9���� �y124�z�@������ǂ�ł��āA���߂ċ��������Ƃ�����B �@���Ƃŕ�e�ƕ�炵�Ă������q���A���炭�Z�ݑ����Ă����Ƃ��o�čs���V�[�����B���ւɌ�����ɏo����e�ɁA�����̂悤�Ȋ����ŁA������Əo�Ă����Ƃ��������~�Ɍ��փh�A���J���悤�Ƃ������q�̔]���ɁA���̏u�ԁA�����������m���[�O���������܂��B���킭�A�q���̂���A��e�̔��^���ς���Ă��܂��ċ��������ƁA���Z�̍��ɖ������ŕ߂܂��āA����ɑ��ċ����Ďӂ��e�̔w���������قǏ������������ƁA�����āA�����q���������߂��A������Ɓu�s���Ă��܂��v�����������Ƃ��Ȃ��������ƁB����̏I�ՁA�قƂ�ǂ�����ƕ`����Ă��Ȃ�������e�̑��݂��A��R�N���[�Y�E�A�b�v����A�����ʂ�A���n���̂悤�ɉ��X���y�[�W�ɂ킽���ĕ�Ƃ̗���������z����Ă����B�����ł悤�₭�n�b�ƂȂ������q�́A��e�ɂ�����Ɗ�������āA���������̂��B�s���Ă��܂��A�ƁB �@���̃V�[���́A�����œǂ߂A�Ȃ�قǂȂ��A�ƈ�a���Ȃ��ǂ߂Ă��܂��̂�������Ȃ����A���������ł́A�����炭���փh�A�������悤�Ƃ���ۂɋ������悬�����u�Ԃ̂悤�Ȏ��Ԃł����Ȃ��͂��ł���A���ꂾ���̗e�ʂ̎�������z���邱�Ƃ͕����I�ɂ͕s�\�Ȃ͂����B �@����ł��A�ӎ���ɂ����܂ł̃G�s�\�[�h��A�����ď��҂����Ă����Ȃ��Ă��A���t�ɂł��Ȃ��͐ς����v���̂悤�Ȃ��̂́A�����̏�ʂł��A�����Ƃ��Ă������������B�����Č������Ă��܂��ƁA������ƌ��t�ɂ���قǁA�����I�ȗ���ɂȂ邵�A���t�ɂ��Ȃ���A�����̏�ʂɉ�������̌`�ɂȂ�B�������čl���Ă݂�ƁA���t���ǂ����Ȃ������ŁA�u�ԏu�ԁA�������̓n�C�E�X�s�[�h�Ȕ��f���J��Ԃ��s���Ă��邱�Ƃ��킩��B�T�b�J�[�ŗD�ꂽ�I��́A�������t�B�[���h��̍����ꏊ������Ղ��Ȃ���A�ǂ��Ƀp�X���o���悢�̂��u���ɗl�X�ȃV�~�����[�V���������Ă���Ƃ������A�����̊��m���A�����悤�Ɍ��t���܂������ǂ����Ȃ����x�ʼn��\�����̎�܂œǂ�A�l�X�Ȍ������݂��肵�Ă���ƕ����B �@�������������Ƃ����ǂ߂Ȃ������ɏ�X����X�������Ă����̂����A�����炭�A������ǂލۂ̔]�̓����́A����̕����̏����̎d���Ƃ͈قȂ���̂ł���͂������A�܂�́A���t�ɖ|�邱�ƂŁA���ꂾ���I���Ȃ��Ƃ�����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��낤�A�ƒ��N�̖��������v���Ŋ��������Ă��܂����B �i II �j 2014�N8���� �y123�z�@�挎�A���̃R�����ŁA�u�����������Ă݂悤�Ǝv���Ă���v�ȂǂƁA�̂����Ȃ��Ƃ��������Ă��܂������ƂŁA�������������ȕ��X����u���������炵�������v�ȂǂƐ����������Ă��܂��A�{����ǂ�ł�������ӑz�O�ɑ����ċh�����Ă��܂����B �@����Ȃ��Ƃ���������ɂ����Ă��킹�Ă��炤�ƁA���́A�����̕��͂����������邱�Ƃɂ����ւ��a���Ă���B���������P�O�O�O�����x�̕��͂Ȃ̂����A����ƌ��̔������炢�́A�u���Ď��͉������������v�ƋC���t���Γ��̕Ћ��ōl���Ă����肷��B �@�Ƃɂ��������n�߂�܂ł���ς��B �@�����A���������Ă����̂��킩��Ȃ��B �@�����ւ�X�g���X�t���ȍ�Ƃ��B �������āA��s���Ƃɉ��s�����肵�Ď������҂����肵�Ă��邠�肳�܂��B �@���������������ꂾ���̂��Ƃŋꂵ��ł������ŁA��Ƃ̐l�����́A�ƂĂ��Ȃ����ʂ̕��͂��A�������������Ă���B �@�����A����������B �@�悢�q�͌����Đ^�������Ă͂����Ȃ��A�Ƃ������a�ȓ��B�q�[���[���̃v���O�����ŗ����퓅����v�������ׂĂ��܂����肳�܂��B �@��Ƃ̐l�����̂Ƃ�ł��Ȃ��l�o�[�E�G���f�B���O�Ń����O�E�A���h�E���C���f�B���O�ɑ����Ă������͂̓��̂ق�̂��������傠����ŁA���łɈؕ|�̔O������Ă��鎩�����Ĕ����������Ă���B �@�����������������Ƃ����܂������Ƃ��A���Ƃ͂����ȒP�ɂ͐i��ł���Ȃ��B�����炭�A�قƂ�Ǒ����~�߂�悤�ɂ��āA�����Ȃ�̑S���_�b�V���Ŕ]��40�x���炢�̌X�Ίp�x�̋}�s�ȍ⓹�������Ă����悤�Ȋ����ɋ߂��B �@����ł��A����Ȃӂ����Ȃ������Ɏ���ڂ�ł������A�Ƃ����v������A�O��̂悤�Ȃ��Ƃ��n�b�^�����܂��ď����Ă݂������͂��������̂́A���܂�ɂ��n�[�h�����グ�����Ă��܂������Ƃɑ����ɋC�t���A���̔��Ȃ���A���߂āA�Ǝv���A�������Ă݂��̂��A���́u�Ȃ�ɂ��e�[�}���l�����ɏ����Ă݂��v�ł���B �@�������ď����Ă݂ĉ��߂Ă킩�������ƁB����́A�������������Ƃ������ƂƁA��������������Ȃ����Ƃ͂܂������Ⴄ�Ƃ������Ƃł���A��҂̋C�������萶����܂ł́A�������ǂ�Ȃɒǂ�����ł݂Ă����l�ȓh��G�̂悤�Ȃ��̂������܂�Ȃ��B �i II �j 2014�N7���� �y122�z�@�i�Z�コ�쎌���ꂽ�Ȃ̃^�C�g���́A�`���̈�s�ڂƓ������Ƃ���r�I�����A�Ƃ����b���āA���M���^�Œ��ׂĂ݂���A�L���ȋȂقǁA���̌X�����m���ɋ������Ƃ��킩�����B �u��������ĕ������v�u����ɂ��͐Ԃ����v�u���グ�Ă�����̐����v�Ƃ�������������ʂǃ��W���[�Ȃ����A�˂Ă���B����́A�T�r����Ȃ��n�܂��Ă��邱�ƂƂ��֘A���Ă���悤�ȋC�����邪�A�Ȃ̃��b�Z�[�W���V���v��������ɃK�c���Ɠ`����Ă���̂ŁA�Ȃ�قǂȂ��ƕςȂƂ���Ŋ��S���Ă��܂��B �@�������A�����Ǝv���������ł��A�r�[�g���Y�ɂ��uCan't Buy Me Love �v�uHey Jude�v�uYesterday�v�Ȃǂ���������A�S�����̍��̏����N�Ƃɂ��u�������Ƃ��Ȃ��ƐS�����Ɓv�Ƃ��uCAN YOU CELEBRATE ?�v����������ƁA���������p�^�[���̂��̂ɂ͖����ɉɂ��Ȃ��B�Ȃ�قǁA�����Ȃ��Ă���ƁA�q�b�g�ȑ��肤���^�̂ЂƂƂł��Ăт����Ȃ��Ă���B�����ď����ł��A�����Ƃ������o���̈�s�ڂɏ����Ă������Ƃ��A����̂܂܂������{�̃^�C�g���Ɏ����Ă��āA���̌�A�^�C�g���ƂƂ��ɁA��i����ςȕ]�����Ƃ����Ƃ����b�������Ƃ�����i���Ȃ݂ɁA���̍�Ƃ���́A�ŏ��̈�s���^�C�g���ɂ����̂ŁA�{���̏����o���ɂ͎g��Ȃ������悤�����A�m���ɁA�{���o�������A������ƌ������Ƃ��Ȃ��悤�Ȉ�ۓI�ȃ^�C�g�����������Ƃ��o���Ă���j�B �@�Ȃ�ł���Ȃ��Ƃ������Ă��邩�Ƃ����ƁA��x�A���������ۂɏ����Ă݂悤���A�Ǝv���n�߂Ă��邩��ł���B���_�A�����ȂNJȒP�ɏ�������̂ł͂Ȃ����A�ڂ̑O�ŕ`�������邱�Ƃ̑�ς�����X��������Ă��鏑����̐l���������Ă���ƁA�������y�͂��݂ɂ���Ȃ��Ƃ����Ă͂����Ȃ��悤�ȋC�����āA�����������Ă������A����ŁA�����������Ƃ����s�ׂɈ�x�ł��A�ق�̂�����Ƃł��Z���Ă݂Ă��o�`�͓�����܂��A�Ƃ����C�����}�����ꂸ�������肷��B�����Ă���Ƃ��A�ǂ�Ȋ����ɂȂ�̂��B���������A�����Ɉ�́A�ǂ�Ȃ��̂�������Ƃ����̂��A�|�����̌������Ō��Ă݂����C������B�����v���āA�����A�����Ƃ�����A�Ȃ�ƂȂ��A�����o���̈�s�͂ǂ�Ȋ����ɂ��悤���A�ȂǂƖ��z���Ă�����悾�����̂ŁA���A�`���̃g�s�b�N�ɔ������Ă��܂����̂�������Ȃ��B���Ȃ݂ɂ���Ȃ��Ƃ��菑���Ă��āA�܂����������n�߂Ă��Ȃ��B �i II �j 2014�N6���� �y121�z�@�m�l���}篐��\���Ԍ�Ɏ�p�����邱�ƂɂȂ�A���������Ƃ��̂��Ƃ��B�s���̑�w�a�@�̏W�����Î��B�����ɁA�S�g����Ë@��Ɍq���ꂽ�ނ������B�����ւ�ȓǏ��Ƃł���ނ��A�A�肪���A���ɂȂɂ��������낢�{�͂Ȃ����u���Ă����B�m���ɁA�����Ȃ�S�g�̎��R��D���A�Ђ�����“���̂Ƃ�”��҂�ԂƂ����̂́A�l���邾���ł������܂�Ȃ��C�����ɂȂ�B�Ȃɂ����邱�Ƃ��Ȃ��ƁA�l���������Ȃ��A����₱���̑z���ɋC���������Ƃɂ��Ȃ�̂��낤�B�ꏊ���A�d�g����d�q�@��̗��p�͋ւ����Ă���B���߂āA�Ȃɂ��{�ł��ǂ�ŋC��킹�����B�����v���͎̂��ɓ��R�ł���B �@�������A�����ł͂��ƍ����Ă��܂��B�ЂƂ́A����ȂƂ��A�ǂ�Ȗ{��ǂ݂������̂Ȃ낤�B���R�A�h�C�L�����͔̂�����ׂ����낤�B�H�ו����o�Ă���悤�Ȃ��̂��A��{�A�_�H�݂̂̏�Ԃʼn߂����Ă���l�ɂ͓ǂނ̂��炢�͂����B�y���ǂ߂āA�����ȈӖ��Ō�Ɏc��Ȃ��悤�Ȃ��̂������̂��낤���B����Ȃ��Ƃ�F�X�ƍl���Ă��āA���ǁA�I�̂́A�V�ď����R�~�b�N�ҏW�҂̕����U���`�������d���}���K�������B �@�ĂяW�����Î��ɕ����߂�A�߂��̏��X�ōw�������ړ��ẴR�~�b�N����n�����Ƃ��ł��āA�����͌��ׂ̉����肽�悤�ȋC�������B���A�Ȃ�ƂȂ��ߑR�Ƃ��Ȃ��v���������ɐ��܂�Ă���B����ȂƂ��ɁA���ꂼ�Ƃ���������E�߂��Ȃ����������Ɍy���V���b�N�����̂��B �@����Ȃ���ȂŎ�p���Ȃ�Ƃ��I���A�悤�₭��ʕa���Ɉڂ��āA�Ăь��������Ƃ��̂��Ƃł���B�p��̏�Ԃ��悢�悤�ŁA�������A��������߂����Ƃ��Ă���ނ������悤�ɖ{�����]���Ă����B�u���܂ł���܂�ǂ��Ƃ��Ȃ��悤�ȏ����͂Ȃ����v�Ɩ���A����ɂ���͑O��̃��x���W���Ǝv�������́A�F�X�l��������A��l�����S�̂̎O���̈ꂭ�炢�܂ŏo�Ă��Ȃ��A�m���t�B�N�V�����d���Ăō\�����ꂽ���b��̊C�O�|����̂�n�����Ƃɂ����B �@�������ē��ɂ킽���āA�^�ɖ{��ǂ݂������Ă���ЂƂɁA�Ȃɂ���E�߂�Ƃ������Ƃ�����Ă݂��킯�����A����͌����ĊȒP�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��A�Ƃ������ƂƁA����ɂ����āA�ЂƂ͊��V�̎��J�̂悤�ɂ��āA�{�����邱�Ƃ����̐��̒��ł��܂��\�S�ɋN���肤��̂��A�Ƃ������Ƃɉ��߂ċC�t�����ꂽ�o�����������B �i II �j 2014�N5���� �y120�z�@�����O�A�Ƃ������A��N���̘b�ŋ��k�����A�N���Ƃ����Α����A�Ƃ������{�Ȃ�ł̖͂��ȕ��K�Ɏ���������Ă݂悤���Ƃ����C�ɂȂ�A�m���̑����ɔN�̐��̂m�g�j�z�[���ɑ����^�B�f���炵�����t�������̂͂�������A���܁A��ۂɎc���Ă���̂́A��l�y�͂ɂȂ��Ė��������Ďn�܂�j���l�l�̓Ə��������B������O�̂��Ƃ����A�t���I�[�P�X�g�����������ɒ����ČȂ̐����z�[�����ɋ�������̂�����A�q��Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B�l�l���l�l�Ƃ��A���퐶���ł͌��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��悤�ȓƓ��̗����p�ŁA���̏u�ԁA�܂��Ɋy��ɂ��������Ȃ������ł����ɂ����̂����A���̑��݊����Ƃɂ����n���p�Ȃ������B �@���̕s�v�c�Ȋ��o�́A���������̗l�q���e���r�Ō��Ă���Ƃ��ɂ������邱�ƂŁA�Ƃɂ����̂��Ă���Ƃ��̊�̊������݂�ȓ����悤�ȋ�C�����܂Ƃ��Ă��āA����Ȃ��牽���Ɏ����ꂽ���̂��Ƃ��������킹�Ă���悤�Ɍ����Ă��܂��B�̑S�̂��g���āA��͂�y��ɕϗe���Ă���Ƃ��납�痈��A����ɂ͂Ȃ������Ȃ�ʋC�z���܂Ƃ��Ă���̂��B �@��S�s���ɂȂ��āA�Ȃɂ��ɑł�����ł���Ƃ��A�ӂ���A�����Ȃ��\��Ƃ������A�Y��̊�������ɕ\��Ă���B�炪�\������R�ɂ������肷��悤�ȉ�H�����āA�S�_�o���ʂ̂��Ƃɔ�₳���B �@���̊��o�́A�������Ђ����珑���i�߂Ă����Ƃ���ɂ����Ă͂܂�̂ł͂Ȃ����낤���B���Ƃ�����A������̐l�����͂ǂ�ȕ\��ŏ����������Ă���̂��낤���B�L���[�u���b�N�̉f��w�V���C�j���O�x�Ŏ����ꂽ�悤�ɂ��ă^�C�v���C�^�[��ł��Ă����W���b�N�E�j�R���\���݂����Ȋ����ɂ��Ȃ����肷��낤���B �@�ӎ��I�A���ӎ��I�Ɍ��t�����̂܂ܔ����Ȃ��珑���Ă���l�����Ȃ��炸����Ƃ����B�悭�����b�����A��Âɍl����ƁA���Ȃ苰�낵�����i�ł͂Ȃ����낤���B�ԂԂƌ����łȂɂ��������Ȃ���A�p�\�R���̉�ʏォ��ڂ𗣂��Ȃ������Ƃ����B�����ŏ����Ȃ���A������A�������肷�邱�Ƃ�����Ƃ����B�����ĂЂƂɂ͌������Ȃ��A����Ȃ���킫��ǂ��\���d����r�����Ȃ����Ԑςݏd�˂āA�悤�₭�ЂƂ̏����͐��܂�Ă���B����Ȃ��Ƃ����߂Ďv���ƁA���������݂𐳂��ēǂ܂Ȃ���A�Ƃ����C�����ɂ��Ȃ����肷��B �i II �j 2014�N4���� �y119�z�@����A����V�ˍ��\�t��`�����f����ς��Ƃ��A�����������|�������B�剉�̔o�D���A����܂ł̃C���[�W��傫���E�p�������������Ă����肵�āA�h�����������ʂ����������̂����A�����ɂ͔ނ��V�ˍ��\�t�Ɍ����Ȃ������̂��B�ł��A�ƍl����B���������V�ˍ��\�t���ۂ������Ƃ��A�|���āA���\�t�ɂ܂�郊�A���e�B���ĂȂ낤�B�܂��A���\�t�̃C���[�W���炵�āA���Ɍy���ŁA������L�����ȕ��͋C�����Ă���悤�Ȋ����A�Ƃ������X�e���^�C�v���ǂ������v�������ׂ邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�v�́A���\�t���ۂ������Ƃ����Ƃ��ɋ����ė����̂́A���̒��x�̂��̂ł��邱�ƂɋC�t���B����ɁA�V�˂����ƁA�ւ������Ă킩��Ȃ��Ȃ�B�Ƃ����킯�ŁA�`���̎剉�̔o�D���V�ˍ��\�t���ۂ������Ȃ��A�Ƃ��������̍����͊ȒP�ɕ��ꋎ���Ă��܂��A���������A���܂��͉������������A�ƂЂƂ�c�b�R�~������H�ڂɑ��������B �@���悤�ɁA�����̂Ȃ��łȂ�ƂȂ��J�e�S���C�Y���Ă��������炵���A�Ƃ����̂́A���������A���ׂĂ̂��̂ɕ~�����Ă��邱�ƂɋC�t���B�Y��������A���t������A�͂Ă͐�l�Ɏ���܂ŁA�ǂ�������q���Ă����悤�Ȃ������芴���ڂ̂��̂ō\������Ă���B�悭�A������ǂ�ł��āA�o��l���Ƀ��A���e�B������Ƃ��Ȃ��Ƃ��Ƃ������b�ɂȂ邪�A���������A���ꂼ��̐l���Ɠ����E�Ƃ̒m�荇�����قƂ�ǂ��Ȃ���A�����A�����Ƃ��Ă��A����ȕ��ɂ��̐E�Ƃ̂ЂƂ́A�݂�Ȃ���Ȋ����Ƃ���ɏ\�c�ꗍ���ɂ��Ă��܂��͈̂��Ղł���A���\�Ȃ悤�Ɏv����B����ł��A�����̂�������������ǂ�ł��āA�����m��Ȃ����E�Ȃ̂ɁA�������Տꊴ�Ɏ�Ɋ����������肵�Ă��邱�Ƃ͊m���ɂ���B���ǁA���������ꍇ�A�ӂ肩�����Ă݂�ƁA�o��l�����A������ۂ������Ȃ��Ƃ������A�����Ӗ��œ��̂̒m��Ȃ��̂���ڂ��Ȋ����̕��������t����ꂽ�肵�Ă��邱�Ƃ������悤�Ɏv���B��̓I�ɂ����ƁA�Ⴆ�Δƍߎ҂��ۂ������Ȃ��ƍߎ҂Ƃ��A�v�͐l�ԂƂ��Ă��̐l���ɂ�����ƌ��������Ă���ꍇ�Ƃ�������悢���낤���B�l�I�ɂ́A���������ǂ�����̍��\�t�ȂH�Ǝv�킹����悤�ȍ앗�̕����A���Lj������Ă��܂����Ƃɍ�����Ȃ���C�t���Ă��܂��A�`���̉f��ň����|�����Ă����������A�ނ���`���[���Ƃ��ĉf���Ă������ƂɋC�t���̂ł���B �i II �j 2014�N3���� �y118�z�@�Ȃ�ƂȂ�����Ă݂��������u�ҏW�҂��邠��v����������B�ЂƂ́A��Ɛ搶�̂Ƃ���Œ����Ђ�����҂���ł���i�e�Ђ̒S�����^�R�����̂悤�ȂƂ���ŁA�������C���C���Ɛ������Ȃ���A���v���W�J���Ă��銴���j�B�����ЂƂ́A�搶�̌��e�����������̂ŁA���M���M���̖������̐Â܂�Ԃ����X�̒����_�b�V�����ĉ�ЂɌ������C���[�W�̂��̂��B���ƂȂ��ẮA��Ƃ��u���̊�������B�Ƃ����̂��A�����Ԃ�O�����Ƃ̕�����̌��e���A�قƂ�ǃ��[���ɓY�t���ꂽ�e�L�X�g�f�[�^�̌`�ŗ���悤�ɂȂ������炾�B�菑���̌��e�����������A�B�M�����镶���̔��ǂɎ�Ɋ���������A�C���[�W�Ƃ͑傫���قȂ镶������������Ƃ̕��̈ӊO���ɂӂꂽ��A�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��H�ɂȂ��Ă��܂����B �@�Ȃ�ł���Ȃ��Ƃ������Ċ����ɂӂ����Ă��邩�Ƃ����ƁA��ʁA��ނł��ז���������l�C����Ƃ���̎d�����������āA�Ռ��������炾�B�����ł́A���l�̃A�V�X�^���g����Ɉ͂܂�āA�a�����Ȃɍ���搶���A�˂��蔫������낵�����Ԃ�ᰂ��Ă���p�����邱�Ƃ͂ł����̂����A�茳�ɂ̓y���������Ȃ������B�S�����A�l�����̉�ʂɌ������A�J�`�J�`�ƃ}�E�X�������肵�Ȃ���G���d�グ�Ă����Ă���B�����A�v���͂��Ƃ��A���l���̐l�����܂ł��A�u�R�~�b�N�X�^�W�I�v�i���̃R�~�X�^�j�Ƃ����\�t�g���g���悤�ɂȂ��������肩�炱�������ɂȂ��Ă���Ƃ����i�t���^�u���b�g�̂ł��������g���Ă���A�V���������j�B������u��Ƃ��邠��v�̂ЂƂA�X�����v�ŏ������������������Ⴍ����Ɋۂ߂Ă�����ւ�ɓ�������A�Ƃ����悤�Ȓ�ԃV�[�������ł͌��邱�Ƃ͓���B �@����ł��A���̖���Ƃ���͗͋��������������B���@�_�͕ω����Ă��A���ǁA�}���p���[�Ŗ��T�̘A�ڃy�[�W�������ɕ������ŕ`���Ă������ƂɂȂ��Ⴂ�͂Ȃ��B������A����Ă��邱�Ƃ͂��܂�ς���Ă��Ȃ��͂��A�ƁB�菑��→���[�v��→�o�b���炢�̕��@�̕ω��ɂƂǂ܂��Ă��镶���̐��E���A���R�����悤�Ȃ��Ƃ�������͂����B���葤�ɍ��{�̕ω����Ȃ��ȏ�A�ǂݎ葤�ɂ��A�h���X�e�B�b�N�ȕω��͋N���肦�Ȃ��悤�ȋC������B�A�i���O�����ăf�W�^��������ł��Ȃ����łȕǂ̂悤�Ȃ��̂��t�Ɋ�]�̌��Ƃ��Ċ�����B �i II �j 2014�N2���� �y117�z�@�R���S�b�̖��ȁu�v���C�o�b�N�o�������Q�v�i����ࠎq�쎌�A�F�藳����ȁj���A������Ȃ��炶�����蒮���@�����A����ȉ̎��������A�Ƃ܂��͋������B�q���̍��A�ܐ߂ɉ��x����������A�������肵���̂̂͂��Ȃ̂ɁA�ׂ����̎��̓��e�܂Œǂ��Ă݂���A���������肵�Ă��Ȃ������̂��B �@�^�C�g���ʂ�A���ݎ��Ői��ł����̂��A���邱�Ƃ����������ɉߋ��i���j�̂��Ƃɔ��ł����B�P�Ԃ̉̎��ł́A�L���ȃT�r�̃t���[�Y�u�n���ɂ��Ȃ��ł�A�������̂�����v���_�@�ƂȂ��āA�ߋ��ɃW�����v����B�����_�ŗׂ̎Ԃ̉^�]�肪�~���[�����������Ƒ����ł���̂ŁA����i�̂���j���{��Ԃ����Ƃ��̌��t�����A��ӁA�ގ��ɑ��ē������t���Ԃ��܂������Ƃ��v���N�����Ă���̂��B �@����ɋ����̂́A�Q�Ԃ̉̎��ł���B�T�r�̂Ƃ���ŁA���x�́u����ɂ��₪��A�o�Ă�����v�Ƃ����t���[�Y���J�[���W�I���痬��Ă���B������āA�܂��A����́A��ӂ̂��Ƃ��v�������ׂ�B���x�̌��t�́A�j�̕����f�������̂Ȃ̂����A�P�Ԃ̉̎��̑����ɂȂ��Ă���ƂƂ��ɁA�Z���t���j���őɂȂ��Ă���ׂ������B���̂悤�Ȃ��Ƃ����đ����ɋN����i�����Ƃ��A���������ł́A���ƂȂɂ������Ă��A��ӂ̂��Ƃƌ��ѕt���čl�������ɂȂ�̂�������Ȃ����j�A�������܂���ɐ^���Ԃȃ|���V�F����������Ă������q�̕����A�����͂����Ă��A�����͗҂������ƔF�߂āA�Ō�͔ނ̂Ƃ���ցu�v���C�o�b�N�v����Ƃ���ŁA�̂��I���B�킸���R��30�b���x�̉̂̐��E�Ȃ���A������Ƃ����Z�҂�ǂ܂��ꂽ�悤�ȏ��ʂł���B������ǂޏꍇ�́A������藧���~�܂��ēǂ߂悢�̂ŁA�����Ȃ�ɃR���g���[���ł��邪�A�̂͑҂��Ă���Ȃ��i�����̉f��ł₽����ʂ̑������̂��������j�B �@����Șb������l�ɂ��Ă�����A���̉̂́A�ق��ɂ�����ȓǂݕ����ł���Ƌ����Ă��ꂽ�B�Q�Ԃɏo�Ă���u����ɂ��₪��v�Ƃ������ƂB�J�[���W�I���痬��Ă����̂̃t���[�Y�Ƃ����ݒ肾���A����́A��c����̉̂����̉̂��ӎ����Ă��āA�����o�čs���̂ł���ނ̋Ȃ̃A���T�[�ɂȂ��Ă���Ƃ����B���v�I�쎌�̋Ȃ������[�X���ꂽ�̂��A�u�v���C�o�b�N�`�v�̂P�N�O�B���܂�̌|�ׂ̍����ɐ��\�N���o�ĒE�X�ł���B �i II �j 2014�N1���� �y116�z�@�[��A�C���t�����獑�{�Éw�̃z�[���ɂ����B�����ēd�Ԃ����߂������p�^�[�����B�m���A�V�؏�w���������ɏ�����B���������䒬�ʼn��Ԃ��āA���}���ɏ�芷���ĉƘH�ɒ����͂��������B�n���܂Ŏd���Ȃ����Ԃ��Ԃ����Ƃɂ������́A�I��c�Ƃ̉w�߂��̃t�@�~���X�ɓ���A�����܂ł̌o�H���l���Ă݂��B��䒬���X���[���āA���̎��̑��ʼn��ԁA�߂邽�߂ɔ��̃z�[���œd�Ԃ�҂����悤�ȋC������B���̂��ƁA�Ȃ���������炢�A����Ȃ��Ƃ��J��Ԃ����C������B���̃z�[���ɗ��ĂA���Ƃ̉w�ɖ߂��Ǝv�������Ƃ��ԈႢ�������̂�������Ȃ��B���̉w�̃z�[�����Α��́A�鋞���̃z�[���ƌ��p�ŁA�������}�s�݂����Ȃ̂ɏ���Ă��܂��A���̂��ƁA�܂����̃z�[���ɗ����Ă�����A���x�͓��C���{���̃z�[���ƌ��p�ŁA���}�ɏ���Ă��܂���������ŁA�Q�������Ă��܂����̂�������Ȃ��B �@���R�Ƃ��Ȃ��܂��́A���ꂩ��o��{�̍Z���Q�������o�����B���O���[�h�ŁA���������̃Q�����ŏ�����ǂނ��Ƃɂ����̂��B �@�����ŁA�܂�������Ă��܂��B�Q�����A�������Ԃ��B�v����ɁA��Ƃ��A���Ȃ�̐Ԏ������Ă����Ƃ������ƂȂ̂����A�����j�ア����Ԃ����炢�Ԃ��B�y�[�W�ɂ���ẮA���̔��������ɂ܂ŋL�q���y��ł����肷��B�������A�Ȃɂ��������̂��A�����̔��͂��B������������l���A���Ȃ��瓏���u���̂悤�Ȋ����ɂȂ��āA��S�s���ɐԓ���������ɈႢ�Ȃ��悤�ȋS�C������̂��������B�Ԏ������ׂēǂݏI��鍠�ɂ́A�t�@�~���X�̕X��������A�i�E���X������Ă����B�C���̒��g���̂��A��̑ł��ǂ��낪�Ȃ����炢�A��m���ׂ����̂������B����Ȃ킯�ŁA���ɍ��g�����C���ŁA�n���d�Ԃɏ�荞���A���̘b�ɂ́A����k�����B�����A���Y��Ƃ���d�b������A�Q���̕������ǂ݂ɂ��������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����l�т̓��e�������B�����A�C�O�ւ̎�ޗ��s���̔�s�@�̂Ȃ��ŁA���Ԃɒǂ��Ă̍Z����Ƃ����Ă����̂����A�r���A���C���Ɋ������܂�A����ł��y���𗣂����A�Z�������ʂ����Ƃ����̂ł���B���̘b�����Ƃ��A��ˎ����搶���A���ɂǂ����Ă��Ԃɍ��킸�A���X�s���̔�s�@�̂Ȃ��ł����𑱂�����b���v���o�����B���R�A����̑̂��炭��[���p���A�������炵�炭�͎���Ɏ����ւ����̂́A�����܂ł��Ȃ��B �i II �j |
|||||||