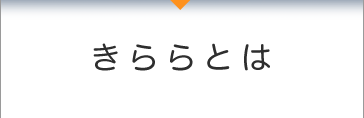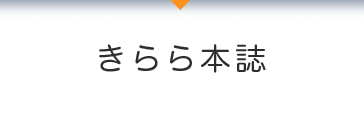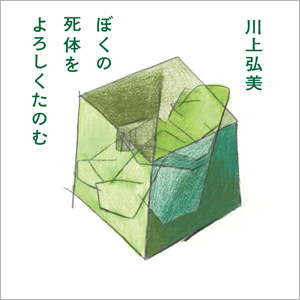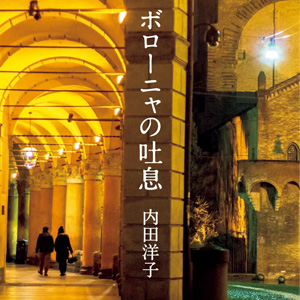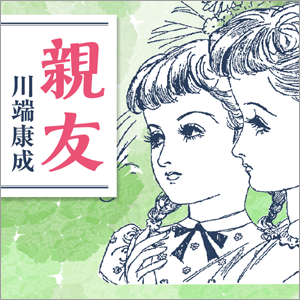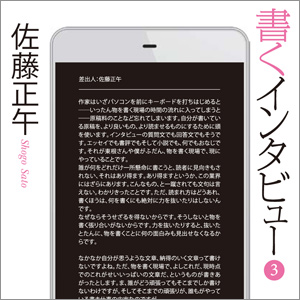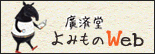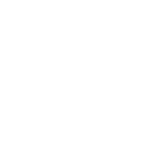| �z�[�� > �����ʐM > 2010�N |

|
|||||||
2010�N12���� �y79�z�u�����v�Ŗ����A�ڂ��Ă��������Ă�������čƂ���́w������̓f�B�i�[�̂��ƂŁx�̒P�s�{�� �P�s�{���A���̂Ƃ��딚���I�ɔł��d�˂Ă���A�ҏW���Ƃ��Ă͑傢�ɐ���オ���Ă���̂����A���҂̓��삳����A�u�A�ڂ��Ă���Ƃ��́w�����x�̓� �҂Ƃ������̂������ӎ����ď����Ă����v�Ƃ������肪�������t�����������A�������܂��܂��S���������ē��X�̎d���Ɏ��g��ł���B �@�����m�̂悤�Ɂw������̓f�B�i�[�̂��ƂŁx��20��̏����Y������l���B�ޏ��͎��͑�������̗ߏ�Ȃ̂����g�����B���Čx�@���ɋ߂� ����A�ޏ��̎����ł����̒j�E�e�R�̐�N�s�����B������Ȃ���A���X�ɓ�����������Ă����B�u�����v�Ƃ��Ă����̖{�i�~�X�e���̘A�ڂƂ������� �ŐV���ȃ`�������W�������̂����A���삳��̂ق��ł��Ⴂ���������C���ǎ҂ł���G���ł̘A�ڂ͏��߂ĂŁA���̕���łǂ̂悤�Ɏ����̍�i��W�J���Ă��� �����Ƃ������Ƃ͏�ɍl���Ă����Ƃ����B����̒S���ҏW�҂���l���̔N��ɋ߂������Ƃ������Ƃ�����A����̐ݒ�Ɋւ��Ẵf�B�X�J�b�V�����̓f�B�e�[�� �Ɏ���܂ŌJ��Ԃ���A���Ȃ薧�x�̔Z�����̂ƂȂ��Ă������B���ꂾ���ɘA�ڂ��X�^�[�g����������S���҂̌��т��傫���B�����Ă��̌������̘A�ڂ̂Ȃ� �ŁA�u�����v�Ɠ���čƂ���Ƃ�����Ƃ̏o��͌����ȉ��w�������N�����āA�w������̓f�B�i�[�̂��ƂŁx�Ƃ����f���炵���G���^�e�C�������g��i�Ɍ� ������̂��B �@���́A�ҏW�҂͍�i�ɑ���ꍇ�A�ǂ̂悤�ɂ����炱�̍�i���ǎ҂̐S�ɓ͂����Ƃ������Ƃɂ������S���Ă���B�u���́v�ƑO�u����u�����Ƃ��� ��͂���ł�����܂��̂��ƂȂ̂����A���Ă��Ď���̊���ȉ��l�ς̒��ł�����������Ă��܂������ł���B�K���ɂ��č���́u�����v�Ƃ����G���ɘA�ڂ� �Ă����Ȃ��ŁA�ǎ҂���̔����Ȃǂ��܂߂āA���̂��Ƃ��������m�F���Ȃ���P�s�{����i�߂邱�Ƃ��ł����B���������Ӗ��ł͎G���͕ҏW�҂ɂƂ��Ă͐��� ���Ɍ������ĊJ���ꂽ�������ł���ƌ����Ă����̂�������Ȃ��B �@���āA��������܂�����čƂ���́w������̓f�B�i�[�̂��ƂŁx�̐V�A�ڂ��n�܂�܂��B���삳��͂ƂĂ����J�Ȏd����������Ȃ̂ŁA���܂��猴�e �����������̂��y���݂Ȃ̂ł����A���x�́u�����v�Ƃ��������̎���������ǂ�ȐV�������w���������܂��̂��A�݂Ȃ��܂��ǂ����y���݂ɂ��Ă��Ă��������B �i I �j 2010�N11���� �y78�z�@���̂Ƃ��납�Ȃ�Z���������̂ŁA�܂Ƃ܂����Ǐ����܂������ł��Ȃ��ł����B����ȂƂ��ɃX�}�[�g�t�H���ł̓Ǐ��������Ă݂��B������u�Ǐ��v�ƌ� �ׂ邩�ǂ����A�l�̒��ł͂܂��������肫�Ă͂��Ȃ����A�Ƃɂ����������̏��������̓d�q���В[���œǂނ��Ƃ��ł����B�@���Ƃ��Α҂��l�����Ă���X�� �ŁA���Ƃ��Ύd������i�������f�X�N�̏�ŁA�������ړ������蕨�̒��ł̑ދ��͂����Ԃ̓Ǐ����铹��Ŋɘa���邱�Ƃ��ł����B����ɂЂǂ��Ƃ� �́A���X�g�����Ŏ��̎M�����鍇�ԂɁA���[�����m�F����ӂ�����āA���傤�lj����ɓ����Ă��Ă����Ȗ�肳����́w����ɂӂ邦�Ă�x����������ǂ�ł� ���B �@���ăX�}�[�g�t�H���ł̓Ǐ��𑱂��Ă��邤���A����̃\�t�@�ł��났�Ȃ��炱�̓d�q���В[���œǏ������Ă��鎩�������Ĝ��R�Ƃ� ���B�������O�œr���܂œǂ�ł��������̑������y����ł����̂����A�l�ɂƂ��Ă͋}�ꂵ�̂��̓Ǐ��̓���ł������͂��̃X�}�[�g�t�H�����A�m���Ɏ����� �Ǐ����鎞�Ԃ̃��[���ɓo�ꂵ�Ă��邱�ƂɁA���̖{�������Ă���ҏW�҂Ƃ��Ă͋��|�����������̂������B �@�Ƃ͂��������_�ł̓X�}�[�g�t�H���œǂ߂��i�͌����Ă���̂ŁA���Z�łȂ���܂��܂��l�̓Ǐ��̎��Ԃ̑唼�͎��̖{�Ő�߂��Ă͂���̂����A����ł��ǂ�ł��āA�y�߂̃~�X�e���[�ȂǁA����̓X�}�[�g�t�H���œǂ߂Ȃ����Ȃ��Ǝv�����肷���i������B �@�����āu���̖{�h�v�̖l�������v�����肷��̂́A�X�}�[�g�t�H���̎��g�݂����ɓǏ�����̂ɉ��������邩��Ȃ̂ł���B���Ƃ��ΑO�o�́w����ɂ� �邦�Ă�x�́A�l���g�p���Ă���g�т̉�ʂł�24��×10�s�̏c�����ŕ\������邪�A����͕��ʂ̕��ɖ{�̂R���̂Q�̃T�C�Y�B������^�b�`�p�l���ł��� ����J���ēǂ�ł����Ƃ��Ȃ�����ɓǂݐi�߂邱�Ƃ��ł���B���́u���ɖ{�R���̂Q�T�C�Y�v�̓Ǐ����A���Ƃ̂ق������̎v�l�̑��x�ɍ����Ă��āA���̖{�� �͖���������Ƃ̂Ȃ��V�����Ǐ��̌��������炵�Ă����̂��B�������d�q���Ђ̐�p�[���̂悤�ɃX�}�[�g�t�H���͏d���͂Ȃ��A�Ў�ł�����ł���B���ܖl �́u���̖{�h�v�A�Ƃ��ǂ��u�X�}�[�g�t�H���h�v�ɂȂ����B �@�������`���ɂ��������悤�ɂ��̃X�}�[�g�t�H���ł̓Ǐ����A�ʂ����āu�Ǐ��v�ƌĂׂ���̂Ȃ̂��l�̒��ł��܂����_�͏o�Ă��Ȃ����A�V���������̌��ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B���̖{�ł͖��킦�Ȃ������������ɂ͂���B �i I �j 2010�N10���� �y77�z�@�ŋ߁A�������̂���������ƍl����������o�������������B����܂ʼn��l���̗D�G�ȏ�����ݏo���Ă������т��鏬���̏܂́A��܂ƗD�G�܂���� ���ꂽ�����A�ǂ���������̊ւ���Ă���܂̂��Ă̎�҂ł������Ƃ������Ƃ��B����l����܂��Ă����܂͂��ꂼ��ʂ̏܂Ȃ̂����A��܂̕��́A�S�N�� �ǑO�n�݂��ꂽ�n�������̂���Â���܂̑�P���҂ł��������A�D�G�܂̕��́A�������ŏI�I�l�������Ă��鏬���̏܂��R�N�O�Ɏ�܂��Ă���������� �̂ł���B��܂̕��͓��������O�ŏ����Ă������������̂ł����ɂ킩�������A�D�G�܂̕��������M����ς����Ă͂������A��i���e�Ɨ����ʼnߋ��Ɏ����� �����I��҂̕����ƒ��Ȃ����ė����ł����B �@�����������ւ�����܂̎�҂̕����A�ēx���̏܂���܂���Ƃ������Ƃ́A���̎��̑I�Ԋ�ɊԈႢ���Ȃ������Ƃ������Ƃ̏ŁA�O�q���� �悤�Ɋ��������Ƃɂ͈Ⴂ�Ȃ��̂����A���̕��������A�����炭���������������邽�߂ɁA�܂����̏܂ɉ��債�Ȃ��Ă͂����Ȃ��ɂ������Ƃ������Ƃ́A�� �W�҂Ƃ��Ă͏����l���Ȃ�������Ȃ�����s��ł���悤�ɂ��v����B �@�����킢�Ȃ��ƂɁA�K�͓I�Ɍ���Ύ������ւ���Ă����ӂ��̏܂�荡��̏܂̂ق����傫���A�m���x�̓_�ł��F�m�x�̓_�ł��D��̂ŁA��܂��ꂽ ����l�̕��ɂ͑f���炵���D�@���K�ꂽ���ƂɂȂ�Ƃ͎v���̂����A�ŏ��̎�܂̎��ɏ�����������������𐮂��Ă����邱�Ƃ��ł��Ȃ��������������ɁA�� ���Ȃ��v�������Ă��邱�Ƃ������ł���B �@���āA���̍��ɏ����̏܂��ǂ̂��炢����̂����m�ɂ͔c�����Ă��Ȃ����A�Ƃɂ������Ȃ葽���̏܂����݂���̂ł͂Ȃ����Ƃ����F���͂���B������ ��̏܂̂悤�Ɍ���̏܂ƂȂ�Ə������Ȃ��Ȃ�Ƃ͎v�����A����ł������̏܂���V���������肪�o�ꂵ�Ă���̂ł���B���̒��ɂ����Ď�܌�� ���������������Ă����Ƃ������Ƃ͐��Ղ������Ƃł͂Ȃ��B��҂͎��̋@������߂āA�܂�����Ȃ�X�e�b�v�A�b�v��_���āA�V���ȏ܂ɉ��傷��B����ɂ� ���Ă͎��������ҏW�҂ɂ��ӔC�͂���Ǝv�����A�Ƃ��������̏����̏܂̐��̑����ɂ��N������悤�ɂ��l������B �u����當�w�܁v��P���҂ł��鍕��L�ꂳ���̏܂ɉ��傷�邱�ƂȂ��A��Q��ڂƂ��Ĕ��\�����w�����q����̒�x�������O�Z���[�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ͎�����Ŋ������B �i I �j 2010�N9���� �y76�z�@�d����̕K�v����iPad��G��悤�ɂȂ��Ă������̐V���̏�����ǂ�ł݂����A���ꂪ���Ƃ̂ق��V�N�ȓǏ��̌��������炵�Ă��ꂽ�B�ЂƂ͗L ���� ���y�Ƃ̃I���W�i���y�Ȃ�����ꂽ���ҍ�i�Ȃ̂����A�ڎ��Ɏ��铱�����ɂ����������̉��y���d�|�����Ă���A���ꂩ��W�J����镨��́A���ɂ��v�� ���[�O�ƂȂ��Ă���B�������d�q���ЂƂ͂����A���C���̑̌��͓ǂݎ肪������ǂ��s�ׂɂ���̂����A�e�͂ɂ���߂�ꂽ�f���炵�����B�W���A���Ƒ� �܂��āA���̉��y�͐����ŐV�����Ǐ��̌��𖡂�킹�Ă��ꂽ�B �@���āA���ꂪ�A�挎���̓����ł����y�������������V�����\���̃W�������ł��邩�͑[���Ƃ��Ă��A����߂Ėʔ������݂ł��邱�Ƃ͊m�� �ł� ��B�������ڂ��͂��̓d�q���Ђ̕�����ǂ����ƂŁA�m���ɖL���ȓǏ��̌��������B���̕����ŕ\�����Ă�����e���A�����œ`����悤�ɂȂ�����A����͂��� �u�Ǐ��v�Ƃ͂����Ȃ���������Ȃ����A�\���I�ɕ�����ǂ��Ȃ��玩���̓��̒��ɂЂƂ̐��E���������Â���̂́A�u�d�q�v�̒��ł����Ă��A��͂藧�h�ȓ� ���̌��ł���ƍl���Ă���B �@����A���鏑�]�Ǝ��Ƙb�����Ă��ď����͂ǂ��ɑ��݂��Ă���̂��Ƃ����b�ɂȂ����B����́A������ɂ���ď��������̎��_�ŏ����Ȃ� ���A �͂��܂��ǂݎ�ɂ���ēǂ܂�ď��߂ď������肤��̂��Ƃ����_�����甭�W�������̂������̂����A�b�̌��_�Ƃ��āA�����͓ǂݎ�̓��̒��ɂ������݂��Ȃ� �Ƃ������Ƃŗ��������B�ӂ��A�����͕����ŏ����ꂽ���̂��A�X��u�����v�ȂǂƌĂ�ł��邪�A����͓ǂݎ�ɂ���ēǂ܂�Ȃ���ΒP�Ȃ镶���̘A �Ȃ�ɉ߂��Ȃ��̂��B �@�d�q���ЂɂȂ�Ə����͏����ł͂Ȃ��Ȃ�Ƃ����������ŋ߂悭�������A�ǂ������̌������͉������̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B��q���� iPad �œǂ�i�͓��ʂƂ��āA�����͓d�q���Ђ̒��ł͂قƂ�Ǘ��̏�ԂŃe�L�X�g�Ƃ��Ēu����Ă���B���̖{�̂悤�ȗ��h�ȑ������Ȃ����A�{�Ƃ��Ă̎�G�� �⎿�����Ȃ��B���̃e�L�X�g�݂̂̏����������͐^�̏����̎p�Ȃ̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B �@�`���ŏq�ׂ����ƂƂ͑������邪�A���̗��̏�ԂŒu����Ă��鏬���i��Ɂu�Ɂv�Ȃǁj��ǂނ��Ƃ��d�q���Ђ������炵���V�����̌� �ł� ��B���������Ӗ��Ō����A�ǎ҂̓��̒��ɂ������݂����Ȃ������́A�d�q���Ђ̓o��ł�肢�낢��ȓ���������Ƃ������ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B
�i I �j 2010�N8���� �y75�z�@�A�����J���C�݂ɏZ�ޒm�l��Twitter��ʂ��Ă��Ƃ肵�Ă���Ƃ��A�X�R�b�g�E�t�B�b�c�W�F�����h�̒Z�ҏ����̘b�ɂȂ����B�ڂ����uThe Lees of Happiness�v�Ƃ�����i���D�����ƙꂭ�ƁA�C�̌������ɂ���m�l�́q���ǂȂ̂ł���������ɓ���Ă݂܂��r�ƕԐM���Ă����B�Q���Ԍ�A���n���Ԃ� �^�钆�ł���ɂ�������炸�A�qKindle�œ���B�Â��Ȏ��Ԃ������f�G�ȏ����ł��ˁr�ƃc�C�[�g���Ă����B�t�B�b�c�W�F�����h�́uThe Lees of Happiness�v�Ƃ����Z�҂͂��܂�L���ȍ�i�ł͂Ȃ����A����������Ɏ�ɓ���ēǂނ��Ƃ̂ł���d�q���Ђ̋@�����ɁA�ڂ��͂��̂Ƃ������������ ���B����ɒm�l�́A�q�A�����J�̏��X�͍���ǂ݂����R�Ȃ̂ł���܂ł͂悭�o�����Ă��܂������A���܂͓ǂ݂����Ƃ��ɒ����ɓǂ߂�d�q���ЂɎ���o���Ă� �܂��܂��r�Ƃ����������Ă����B���̂悤�ɁA�Ǐ��Ƃł��菑�X�D���ł��������m�l�ł����A�d�q���Ђ̖��͂ɂ͍R�����������̂������Ă���炵���̂��B �@�d�q���Ќ��N�Ƃ����Ă�����{�A�܂����R�ɐV������ɓ���邱�Ƃ̂ł���{�i�I�v���b�g�z�[�����o�����Ă��Ȃ����߂��A�\�ʏ�͉��₩ �ɐ��ڂ��Ă���悤�Ɍ����邪�A���̒m�l�̃c�C�[�g�ɂ�����悤�ɁA���������Γd�q���Ђŏ�����ǂގ���͂��������܂ŗ��Ă���悤�Ȋ���������B�� �Ȃ݂ɐ��C�݂̒m�l�́A�qKindle����iPad�̂ق����ǂ݂₷���B������Əd���̂���_�ł����A��ʂ����邭������ȒP�B�d�q���Ђ̐��� Kindle�̂ق��������̂ŁAKindle �Ń_�E�����[�h�������̂�iPad�œǂ�ł��܂��r�Ƃ̂��ƁB���̔���������킩��悤�ɁAKindle�͂����܂Ŗ{������ł���A�ǂޓ���Ƃ��Ă� iPad�����̎���̍����߂Ă��������ȋC�z�ł���B �@�ڂ���iPad�������G��悤�ɂȂ������A���̒��ŏ�����W�J����ƂȂ�ƁA���͂��낢��Ȃ��Ƃ��ł���B���镶�͂̂Ƃ���܂ŗ���Ɖ������o�� ����f���𗬂�����ȂǁA�����Ɍ��t�����ł͂Ȃ��A����f���̗͂����������V�����\���W�������������ɐ��܂�Ă������Ȋ���������̂��B���̂Ƃ������ �u�����v�ƌĂԂ̂��͕ʂɂ��Ă��A�Ƃɂ������t���j�Ƃ����V�����\�����ǂ�ǂ�o�����Ă���悤�Ɏv����B���̂��Ƃ������y�����v���Ă��鎩�������邱�� ���������B�Ƃ͂����A���̃X�R�b�g�E�t�B�b�c�W�F�����h���A������f���̂��������̍�i���ǂ��v�����́A�ڂ��ɂ��܂������킩��Ȃ��B �i I �j 2010�N7���� �y74�z�@���̂Ƃ���d�q���Ђ̂��Ƃ������ƍl���Ă���B���̖{����d�q���ЂցA���̗���͐��������Ď~�߂��Ȃ��Ǝv���B�ǎ҂̗����A���ʃR�X�g�A���� ��� �ǂ��낢��Ȋϓ_����l���Ă݂Ă��A�d�q���Ђ̗D�ʂ͂�邪�Ȃ��B�������g���d�q���ЂŎ�y�ɌÍ������̖��쏬�����ǂ߂���f���炵���Ǝv���Ă��邵�A�� �܉Ƃɂ��ӂ�Ă��鎆�̖{���c�u�c�̃p�b�P�[�W���炢�̃^�u���b�g�ɂ����܂��Ă��܂��Ƃ����̂͒ɉ��ł�����B�����A��������͓`���E�l�݂����Ȃ��̂ɂ� �邵���Ȃ��̂�������Ȃ����A�����Ƃ��Ă͍��サ�炭�͎��̖{�ɂ�������Ă݂����Ƃ����v��������B �@�d�q���Ђ̎���ɕҏW�҂��邢�͏o�ŎЂ͂ǂ��ւ���Ă����̂��Ƃ������́A���ܓ��Ǝ҂��W�܂�ƕK���b��ɂ������̂����A�F������ �Ƃ��� ���y�ϓI�ɂƂ炦�Ă���B�����������Ƃ��Ă͂��̖����ɂ��Ă͂��܂܂ł̂悤�Ȃ������Ő��ڂ��Ă������Ƃ͂Ȃ����낤�ƌ��Ă���B�ҏW�҂�o�ŎЂ����� ��̂́A�����������X�L�b�v���Ē��앨�����̒��ɏo�Ă������Ƃ��B�v�d�a���ʂ̊�{���O�ł��郍���O�e�[���Ƃ����l�����炢���A����͕K��̎��ԂɂȂ� �Ǝv���B���̂Ƃ��ɂ����͂ǂ��ւ�邱�Ƃ��ł���̂��A�l�ɂ�����̓R���e���c�̋����J���҂ɂȂ�悢�Ƃ����ӌ�������B�����A���ꂩ��̏o�� �Ђ̎d���͒���҂Ƃ̗ǍD�ȊW���ێ����Ă����Ȃ���̃R���e���c�J�����ƌ�����l�Ԃ�����B����������͂����ɂ��ҏW�ғ��L�̑���Ȍ������ɉ߂���� �ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B �@�d�q���Ђ̎���ɂ�����o�ŎЂ̖����͂܂��̓R���e���c�̔̑��v�����[�V�����ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B�������R���e���c�J�������肤��Ƃ͎v�����A����͂₪�ďo�ŎЂ���͕������āA�O���ł����Ƃ���̃G�[�W�F���g�̂悤�Ȃ��̂ɂȂ��Ă����悤�ȋC������B �@�܂艽�����������̂��Ƃ����A�R���e���c�̊J���Ƃ����̂͂���߂ăp�[�\�i���Ȏd�����Ƃ������Ƃł���B���������g�D�����Ă��� ���� ��A���̂Ƃ��͂ƂĂ���ɕ����Ȃ����̂������オ���Ă���悤�ȋC������B�d�q���Ђ̎���Ƃ����̂͌̐��_���̐��_�ƒ��ڏo��ꏊ���^�����鎞�� �Ƃ����ӂ��ɂƂ炦�Ă���B�����Ă��̏ꏊ�ɗ������̂���͂�u�v�ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł���B�����Ȃ���͂⎩�������̖{�ɂ�����闝�R���Ȃ� �Ȃ��Ă��邩������Ȃ��B �i I �j 2010�N6���� �y73�z�@�������̂Łu�����v�����̍�����V�N�ڂɓ���B�n�������炸���Ƃ��̗������������Ă��Ă���̂ŁA�����73��ځB���炽�߂Đ����������Ă݂� �ƁA���Ȃ���悭�������܂ŏ����Ă����ȂƂ͎v���̂����A���͂���قlj���d�˂Ă����Ƃ��������͂܂�łȂ��B�Ȃ����ƌ������̗��ł͂������� �������Ƃ������Ă����悤�ȋC�����邩�炾�B �@�z�[���y�[�W�́u�v�d�a�����v�ł͂��̗����܂Ƃ߂ēǂ߂�悤�ɂȂ��Ă��āA����܂ł�72��ʓǂ��Ă݂�ƁA�����̍l���Ă������Ƃ����悻�� ����Ă��Ȃ����Ƃɋ����B�܂��i�����Ȃ��Ƃ����ΐi�����Ȃ����ƂɂȂ邪�A�����Ƃ͉����A�����ɂƂ��ď����Ƃ͂ǂ��������̂Ȃ̂��A���̂��Ƃ������Ƃ��� ������ď��������Ă������肾�B �@���܂��猾���܂ł��Ȃ����A�����Ƃ͌��t�ł����Ă���B���܂͂����Ɉ������Ă���͓͂����Ă��邪�A���Ă͌�����l�X�ɓ`�����Ă����B ������u�����v�ƌĂԂ��ɂ��Ă͂��낢��ȍl��������Ƃ͎v�����A�����̌��^�ł��邱�Ƃɂ͊ԈႢ�Ȃ��B�₪��15���I�Ƀh�C�c�̃O�[�e���x���O�ɂ�� ���ň���Z�p���l�Ă���A�����́u�����ꂽ�{�v�ƂȂ��đ����̐l�̎�ɓn��悤�ɂȂ����B�܂肱���Ţ�b�����t�����u�������t�v�ւ̓]�����s��ꂽ�� �ƂɂȂ�B�����Ă���܂Ōl����l�ւƓ`�����Ă������̂��A�l����s���葽���́u�ǎҁv���������̂ɂȂ����B�E�ƂƂ��Ă̏����Ƃ����藧���� �����̂����̈���Z�p�̔��B�ɂ����̂��傫���B �@���āA���̗��łU�N�ԏ��������Ă����A�����Ƃ͉����Ƃ�������ł���B���̓����͊ȒP�Ɍ����Ă��܂��A�u�y���݁v�Ƃ������Ƃɐs����B �@�����ǎ҂̑����珬���Ƃ������̂ɃA�v���[�`���Ă������A�ǂފy���݂��Ȃ���Ώ����͑��݂��Ȃ��ƍl���Ă���B�����Ă��̓ǂފy���݂Ƃ����̂́A�u�� �����t�v���y���ނƂ������ƂƓ������ƍl���Ă���B�������u����v���y���ނƂ������Ƃ������ł͂ł���B����������͉f���║��ł�����ł�����̂ł� ��A���������ŗL�̊y���݂́A�����܂Łu�������t�v���y���ނƂ������Ƃł���ƍl���Ă���B �@�������ׂ��d�q���Ђ̎���ł����̊y���݂͕ς��Ȃ��Ǝv���Ă��邪�A�u�������t�v���̂ɂ��ω����N����悤�ȋC�����Ă���B���̂Ƃ��ɂ��A���܂ł��u�����ꂽ�{�v����������Ƃ��ł��Ȃ������̎p��������B �i I �j 2010�N5���� �y72�z�@���܂���10�N�قǑO�̂��Ƃ��B�A�����J�ݏZ�ŁA�������łX�P�P�̓��������e���ɑ��������W���[�i���X�g�̗F�l���A�Ђ��т��ɗ��A�肵�ē����ʼn�� ���Ƃ��A�ނ��o�b�O���疼�h����������傫�������悤�Ȕ������������o�����B���Ɏg���̂��܂������킩��Ȃ������l�ɁA�F�l�́u���̒��ɂb�c���\������ �̉��y�������Ă���B�o���ɏo��Ƃ��͂���ЂƂ����Ă����}�[���[��10�̌����Ȃ����đS��������v�Ə����ւ炵���Ɍ�����̂��B�����܂ł��Ȃ����� ���A�l��iPod�Ƃ����g�ь^�f�W�^�����y�v���C���[�����ۂɌ����ŏ��̏u�Ԃ������B���ꂩ�炷���ɖl�����̃V���v���Ȗ��@�̏�������ɓ���āA���܂ł� �Ƃ̒��ł������y�͂���ł��������Ȃ��Ȃ��Ă���B �@���āA���̂Ƃ��돬���Ƃ̕��Ɖ�ƕK���b��ɂȂ�̂��A�u���̖{�͂Ȃ��Ȃ�̂��v�Ƃ����C�V���[�ł���B�C�̌������̃A�����J�ł́A�� �N�ɓ����ĐV���ȓd�q���В[�����o�ꂵ�āA���ł�200����ȏ㔄��Ă���Ƃ�����L���h���ƂƂ��ɁA�l�X���{��G����V�����f�W�^���œǂގ���ɓ��� ���Ƃ����F�������܂����B���{�ł́A�܂����{��Ή��̖{�i�I�[�����o�ꂵ�Ă��Ȃ����Ƃ�d�q���Ђ̎s�ꎩ�̂��������Ȃ��߁A�����ٍ��̘b�̂悤�ɂ� �������邪�AiPod�̂��Ƃ��l����ƁA������d�q���В[���œǂގ���͂��������܂ŗ��Ă���Ƃ����͂Ђ��Ђ��Ɗ�����B �@���̂��Ƃɑ��āA�����Ƃ̕��X�̔����ɂ͂��܂��܂Ȃ��̂�����B���������f�W�^���Ή��̐V���������̂�������͍�����l�A�d�q���В[���ɂ͐�� �Ɏ����̏����͍ڂ��Ȃ��Ɛ錾����l�i�l�Ƃ��Ă͈��|�I�ɉ����������j�A���̂ق��ɂ������Ɠd�q���В[���̐e�a���Ɋւ��č��{�I�ȋ^���悷��l�Ȃǂ��� ����Ȉӌ����B�u���̖{�͂Ȃ��Ȃ�̂��v�Ƃ�������ɂ��Ă��A�u�Ȃ��Ȃ�Ȃ��v�Ƃ���l�����吨�����A���ꂪ���܂��K�͂͏����Ȃ��̂ɂȂ��Ă��� ���낤�ƒN�����S�Ȃ炸���v���Ă���i�₵�����Ƃ����j�Ɩl�͊������B �@�ق�Ƃ��ɂ���10�N��iPod�̂��Ƃ��l����ƁA�L���h����iPad�ŏ�����ǂނ��Ƃ�����I�ȕ��i�ɂȂ邱�Ƃ͕s���̂��Ƃ̂悤�Ɏv���� ���A���̂Ƃ��ǂ�ȏ������ǂ܂�Ă���̂����A���͖l�͂����ւ�C�ɂȂ��Ă���B�u���̖{�v�ł����������Ȃ������Ƃ������̂�����Ƃ���Ȃ�A�ʂ����� �d�q���В[���ł�����͐����c���̂��A�����S�z�ł���B �i I �j 2010�N4���� �y71�z�@���I�̉��Ɂu���E�̕��w�v�Ƃ����S50���̕��w�S�W�����ׂĂ���B�X���C�h���̏��˂Ȃ̂ŁA�ӂ���͂��̑O���ʐ^�W�Ȃǂ̑唻�̖{�����������Ă���̂����A�Ƃ��ǂ���������o���Ă͂��̕��w�S�W���J���Ă͂���B �@���������w���̍��A����̑O�ɂ��������X�ɗ\�����āA�����z�{�����̂��y���݂ɂ��Ȃ���ǂS�W�ł���B���^����Ă��邠�炩�� �̍�i�ɖڂ͒ʂ��Ă���̂����A�Ȃɂ��͂邩�̂̓Ǐ��̌��Ȃ̂ŁA�ׂ��ȓ��e�ɂ��Ă͂��Ȃ肠��ӂ�ŁA���܂̎d������������P�����ēǂ��悤�Ǝv�� �Ă���B �@�܂��A���ꂪ���݂̂Ƃ���́A�킪�B��̕ҏW�҃��^�C�A��̐l���v�Ȃ̂����A���̊y���݂̂��߂ɂ��A���̑S50���͏��I�̉��ɒ������� �Ă����Ȃ�������Ȃ��B���܂ł͂߂��炵���Ȃ���������̗��h�Ȗ{�Ȃ̂ŁA�ʐ^�W�̗��Ƃ͂������I�̂��Ȃ�̕��������̕��w�S�W����߂Ă���B�������l ���Ō�̖L���ȓǏ������̂��߂ɁA���̑S50�������I����Ǖ����悤�Ǝv�������Ƃ͂��܂܂ň�x�ƂĖ����B �@�ŋ߁A�u�L���h���v�Ȃǂ̓d�q���В[���̓��{�㗤���b��ƂȂ��Ă��邪�A�������{�ł��o�Ėl�̈������Ă���S�W���d�q���ЂƂ��Ď��^����邱�ƂɂȂ�A����͏�����20�Z���`�l���̒[���̒��ɔ[�܂��Ă��܂��炵���B �@�����Ȃ�ΑS50���̕��w�S�W���g�тł���킯�ŁA����͂���ŕ֗��Ȃ��ƂȂ̂�������Ȃ��B���s��ł�����ЂƂ����Ă����A�u���E�̕��w�v�̍D�݂̍�Ƃ�S50���̒����炢�ł��ǂ��łł��I��œǂ߂邱�ƂɂȂ�B �@�����A���̓Ǐ��̌����A���ď��X�ɗ\�����āA�������ꂪ�z�{�����̂��y���݂ɑ҂��Ȃ���ǂ��ƂƓ������̂��Ƃ͌����Ȃ����� ���B�ʂɏ����ɑ��Ă̕Έ��͎������킹�Ă͂��Ȃ����A��͂�{�œǂނ̂Ɠd�q�[���œǂނ̂Ƃł́A���̓Ǐ��̌��ɂ͌���I�ȈႢ��������ɂ������Ȃ��B �@���Ƃ��Ō�̂ЂƂ�ɂȂ��Ă����͓d�q���Ђł͏����͔��\���܂���Ƃ�����Ƃ̕��ɐ������������A����͂��̐l�����܂܂Ŗ{��ʂ��� ����߂ĖL���ȓǏ��̌���z���Ă�������ł���Ɗ������B������֗��Ƃ͂����A�u���E�̕��w�v�͂�͂�d�q���В[���ł͂Ȃ��A�́A��ɓ��ꂽ�{�œǂ݂��� ���A���̂ق����Ǐ��̌��͂��[�����Ă����悤�Ɏv���B �@�Ƃ������ƂŁA�}���P�X���p���F�[�[�����u���O���G�����I�̉��ŘV��̖l��҂��Ă���B �i I �j 2010�N3���� �y70�z�@����~�̒�������A�������͂邩�ɎႢ�����ƂƊȒP�Ȓ��H���ς܂������Ƙb���Ă����Ƃ��A�u�ʂ����Đl�Ԃ��܂������o�ꂵ�Ȃ������͉\���v�Ƃ� ���b�ɂȂ����B�ݒ�Ƃ��Ă͐l�ނ��܂��������ɐ₦�����̒n���A���邢�̓l�b�g�̒��ŋN���Ă�����̗��ʁB�ЂƂ�̐l�Ԃ��o�ꂳ���邱�ƂȂ��A�����W �J���邱�Ƃ͉\�Ȃ̂��Ƃ����b�ɂȂ����B �@���_���猾���A����͐�ɕs�\�ł���Ƃ����n�_�ɁA�H��̋C�܂���ȋc�_�͒B�����B�����͂����܂ł��Ȃ����t�ɂ���ď������B�� �̌��t�������̂͐l�Ԃł���B�n���A���t�͒P��Ƃ��đ��݂��Ă����Ǝv����B���ꂪ�W�܂蕶�͂��`�����Ă����ƂƂ��ɕ��ꂪ���܂�Ă����B����A�� ����������l�Ԃ͕������邽�߂ɕ��͂��J�����Ă������̂�������Ȃ��B������ɂ��땶�͂ƂƂ��ɐ��܂ꂽ����́A���̌�A�����̓o��Łu���v���Ƃ��� �u�����v���Ƃɐi�����Ă����A�悤�₭�����Ƃ����W���������a�����邱�ƂɂȂ�B �@���Đl�ނ����ɐ₦�l�Ԃ��ЂƂ���o�ꂵ�Ȃ������A���邢�͓d�C�M���̂Ȃ��Ő���������̍s���������E�A������“���͉�”���邱�Ƃ͂ł���� �v���B�P�Ȃ錾�t�̗���A���邢�͕��̗͂ɂȂ邩������Ȃ����A�Ƃ������������Ƃ͉\�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ƃ������ƂɂȂ����B�������ʂ����Ă��ꂪ���� �ƌĂׂ���̂Ȃ̂��Ƃ����Ƃ���ŁA�Ⴂ�����Ƃ͂���ȊT�O�����������Ă����̂��B�l��菭���N��̂�����S��������̍�Ƃ��A�����ɂ��Ă������� �ɂ����������Ă���Ƃ����B �u�����Ƃ́A�l�Ԃ��������̂ł���v �@�Ђǂ�������O�̍l���������A���̎��̖l�́A�u�l�Ԃ͎��ɂ䂭���̂ł���v�Ƃ����^���Ɠ������炢�̋������A���̔����Ɏ������B �@�����␢�E��`���̂ł͂Ȃ��A�l�Ԃ������B�����l�͂������|���B�X�g�[���[��W�J��`���̂ł͂Ȃ��A�l�Ԃ�S���������̂��ƁB �@���t���A�l�Ԃ������������̂ł������A��������g���ĕ\�����鏬���́A�l�Ԃ���Ў���������Ȃ��B���t���l�Ԃ̈ӎ���ʂ��Ĕ���������� �ł������A�l�Ԃ͕���⏬���̎�O�ɕK�����݂��Ă���̂ł���B�܂蕨��⏬����������菑�����肷�邱�Ƃ́A���ɓI�ɂ͂��̎�̂���l�Ԃ�`������ �ɑ��Ȃ�Ȃ��B�ł̓R���s���[�^�����������ł͂ǂ��Ȃ�̂��A�Ⴂ�����ƂƂ̋c�_�͒������肪�Ƃ��ɉ߂��Ă��A�܂������Ă����B �i I �j 2010�N2���� �y69�z�@�f�������߂āu����v�Ƃ������̂��̂́A�P�X�O�Q�N�t�����X�̃W�����W���E�����G�X�ɂ���ċr�{�E�ē��ꂽ�w�����E���s�x�Ƃ���14���̉f�� ���Ƃ���Ă���B���̍�i�͑�C���甭�˂���Č��֍s�����l�Ԃ����̒n��“���l”�ɏo��Ƃ������̂ŁA�X�g�[���[�̂��ƂɂȂ����̂̓W���[���E���F���k �Ƃg�E�f�E�E�F���Y�̉��{���̂r�e�����ł������Ƃ����B �@��������͂܂��f��̓T�C�����g�ł���A�����͂Ȃ��f���݂̂��W�J����Ă������̂ł��������A����܂ł̔n���삯����D�Ԃ��������� ���邾���̂����錩�����I�f������E�p���A�l�Ԃ̒m�I�z���͂����͂Ɏh������u�f��v�Ƃ������̂��o�������̂ł���B���N�A�����J�ł��w���ԋ����x�� �������ꐫ����������i�����J����邪�A�����G�X�́w�����E���s�x�����F���k�ƃE�F���Y�̏��������~���ɂ��Đ��܂ꂽ�Ƃ��������́A���̌�̉f��Ə����� �W���l���邤���łƂĂ������[���B �@�l���Ă݂�Ώ����̓����G�X�̍�i����n�܂��āA����܂ʼnf��ɐ��X�̌�����������Ă����B�g�[�L�[����ɓ���o��l�����Z���t����悤�ɂ� ��ƁA�����̒��̕��͂⌾�t�����̂܂܉f���̒��Ɉڂ�������ꂽ�B���������̕��͂⌾�t�͂��łɏ����ł͂Ȃ��̂��B�����͉f����^����ꂽ�Ƃ���ɐ����| ����ꂽ�n�����̂悤�ɂ�������ς��Ă��܂��̂ł���B�悭����ɒ����ɉf�扻����Ă���Ƃ����f��]�Ȃǂ��������邪�A���͂���Ȃ��Ƃ͂��肦�Ȃ��B�� ���͉f���̒��ɂƂ肱�܂ꂽ���_�ŏ����ł͂Ȃ��Ȃ�̂ł���B �@�悭�����Ƃ������̍�i�̉f�扻�ɍۂ�����ɒ����ɂȂǂƂ��������������肷�邪�A����͂ǂ��������Șb�Ȃ̂ł���B�����Ƃ͉f��ɍ�i��� �������_�ŁA���̍�i���ǂ��Ȃ낤�Ǝ���R���g���[������̂͒��߂�ׂ��Ȃ̂ł���B�����Ă��������̍�i���ɂ��悤�Ƃ���̂Ȃ�A�f��Ɍ����� ����̂͒f�ł�߂�ׂ��ł���Ǝv���Ă���B �@�Q�O�P�O�N�͂R�c�f��̌��N�Ƃ����Ă���B�]���ɂȂ��Ă���n���E�b�h���R�c�f����ς����A�f��͂��̑��n���ɋ삯��n����������������Ă��� �D�Ԃŋ��������肵���̂Ɠ����悤�ɁA�܂��܂��������I�ɂȂ��Ă���Ɗ������B���̒��q�ł����Ήf��͂����������畨���K�v�Ƃ��Ȃ��Ȃ邩������Ȃ��B ���̂Ƃ������͍Ăщf��𗽉킵�A�u����̉��v�Ƃ��ĕ������ʂ������Ƃ��ł��邾�낤���B �i I �j 2010�N1���� �y68�z�@�Ⴂ���A�����o���̐��\�s���}����قLj��ǂ�������������A���́A��ɐ��E�I���w�܂��邱�ƂɂȂ鏬���Ƃ���������]�I�ȐN�̕�����A ���M�̍����ʼn����r�߂邩�̂悤�ɉ�����H��Ȃ���A�����œW�J����錾��̌Q��������Ȃ�ɓ��̒��ʼnf���Ɉڍs���悤�Ǝ��݂����Ƃ��������i���̕��͂� ���̏����Ƃ��N�ł��邩�͑���@���͂��Ǝv���j�B�@ �@���͂��̏����́A���\���ꂽ�P�X�U�O�N��Ɉ�x�f�扻����Ă��邪�i���̏������f���ɂ���Ȃ�đ�ςɗE�C�̂���s�ׂ��j�A�ŋ߁A�悤�₭����~�j�V�A�^�[�̘A����f�̈�{�Ƃ��ĉf�扻���ꂽ��i���ς邱�ƂɂȂ����B �@����܂ł��܂�f��قŏ�f����邱�Ƃ��Ȃ��������A�������c�u�c���Ȃǂ̘b�����������Ƃ��Ȃ��������̍�i�����A�����悤�Ȏ�|�ʼn��ɑ����^��ŗ��Ă������ǂ����͂킩��Ȃ�����ǁA�ϋq�Ȃ͎����Ƃقړ��N��̊ϋq�𒆐S�ɗ]���Ƃ���Ȃ����܂��Ă����B �@�f��́A�`�����珬���̕��͂����̂܂܈��p���Ďn�܂����̂����A���̎��_�Ŋϋq�Ȃɂ͂��łɎ����N���Ă����B�f���ł͂P�X�U�O�N��̓� �{���f����Ă����̂����A����ɂ��Ԃ��ꂽ�����̕��͂͌ÐF���R�̊�������A�o�D�����̓��̂���Č���鏬�����̌��t���V���Ă��邩�̂悤�� ���A���e�B�����������Ȃ����̂������B�����Ɣ����I�߂��͂����Ă���̂�����A����������̂Ȃ����ƂȂ̂�������Ȃ����A�f�����Ƃ��Ȃ������́A�܂��͓� �̉����ꂽ����́A�͂Ȃ͂������������ۂɂ͂Ƃɂ����������肾�����B�@ �@�f����ςĂ����������������߁A�Ƃɖ߂肻�̏��������I�����������o���ēǂ����̂����A�f��Ŋ������u�����v�͏����ł͂��������������A�ނ���f������̂ɂ�����Ȃ߂�ꂽ���͂⌾�t���A���炽�߂Ċ����̊C�̒����畂���яオ��A�P�������߂����̂ł���B �@�����͌���̌|�p�ł���B���ꂪ�f���Ɉڂ�������ꂽ�Ƃ��̐Ǝコ�ɁA���ׂĂ̏����̏�����͌x���S�������Ȃ�������Ȃ��B�����Ɖf�� �͕ʂ̂��̂Ƃ��ċ����Ȃ�������Ȃ��B�₷�₷�Ɖf��̒��ɏ����̕��͂⌾�t�����p�����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����Ƃ͉f���̗͂���邱�ƂȂ��A���͂⌾�t�� �͂����Ő��E���\�z���Ȃ�������Ȃ��B���̂��߂Ɍ���̗͂��̂��B �@�Ƃɖ߂��}����قlj����Ă��������̏����o����ǂ݂Ȃ���A���炽�߂ĉf���Ȃǂɕ�������̂��ƓƂ�v���̂������B �i I �j |
|||||||