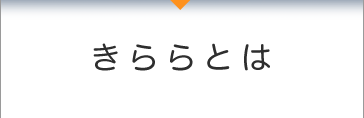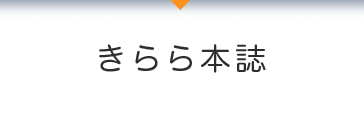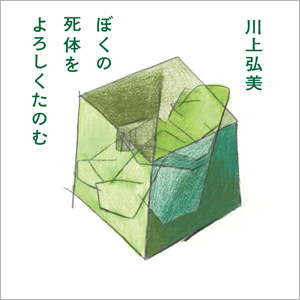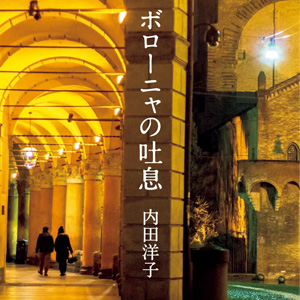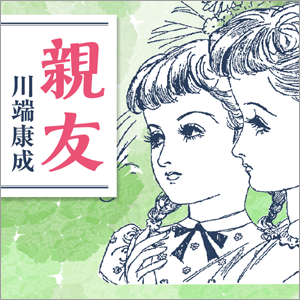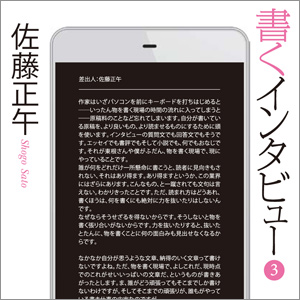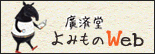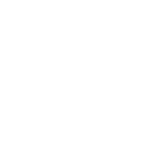| �z�[�� > �����ʐM > 2015�N |

|
|||||||
2015�N12���� �y139�z�@���łɎ��ʂ�ǂ܂ꂽ���͂��C�Â����Ƒ����܂����A�ufrom BOOKSHOPS�v������12�����ōŏI����}���܂����B�u�����v�̑n�����珑�X���݂̂Ȃ��܂ɂ͂��͓Y�������������A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B �@�w������ɏ��X�ŃA���o�C�g�����Ă������Ƃ�����قǖ{�����D���ŁA���X������̕ł�S���ł������Ƃ��������A�o�����Ăق�ق�́u�����v��Ў�ɁA�L��S���̋C�����ŏ��X���э��݂ʼn�����̂����ł͉��������v���o�ł��B �@���X������̂��E�ߖ{�R�������x�[�X�Ɏn�܂������̕łł������A�V�K�I�[�v���̏��X����ނ�����A�����n���k��Ə̂��āA�n���̏��X������ɏW�܂��Ă�����������A���؏܁E�H��܂̔��\�ɍ��킹���L�����f�ڂ�����B���̎����̎��́u����̔M�v�����`���������Ƃ����v���ŁA���܂ŕҏW�����Ă��܂����i�u�v�d�a�����v�ł͂܂������̋L����ǂނ��Ƃ��ł��܂��j�B �u�����v�̖������ɂȂ����u���X������~��Ƃ���v�̓C�k���A���ꂾ������d�˂邱�Ƃ��ł����̂��݂Ȃ��܂̂������ł��B�C�k�����������ɂ��̂��l���ɐG��A���Ђ��d�������ꏏ�������ƁA�����̎��M�����肢������Ƃ̕�����������Ⴂ�܂����i��N���̘A�ڂ��o�āA���̒P�s�{���������Ɋ��s����܂��j�B �@���̏\�N���̊ԁA���X���݂̂Ȃ��܂Ɩ��x�̔Z�����t�������������Ă��������A���ӂ̋C�����ł����ς��ł��B���Ƃ肪���������ɁA�v���[�t�{�̊��z��S���ҏW�҂����^����ɑ����Ă�������悤�ɂȂ������B�����e��������Ƃ���̂��Ƃ�M������Ă�����A�́A�����ɂȂ��ēǂƂ����R�~�b�N�{�𑗂��Ă����������������܂����i���ł��厖�Ƀf�X�N�̒I�ɓ���Ă��܂��j�B���X�ł�ʂ��Čq�����������ŁA�����g�̕ҏW�Ґ������ʂ�L���Ȃ��̂ɂȂ�܂����B �@���X�ł͂���������܂����A���C�^�[�̑�䒩�������S���̐V���C���^�r���[�uPick UP�v��A�ِΒ��i����̃R�~�b�N�G�b�Z�C�u�{�̗d���@�v�v�R���O�Y�v�́A������A�ڂ������܂��B�M��C���^�r���[�̓C�k���A���ʊ��Ƃ��āA�Ђ������ƕ������邩������܂���B���̎��͉������}������Ă��������܂��ƍK���ł��B �@���ꂩ����u�����v�������ǂ��������܂��Ɗ������ł��B�����ĉ�����낵�����肢�\���グ�܂��B �i�ufrom BOOKSHOPS�v�S���^���j 2015�N11���� �y138�z�@�x�݂𗘗p���ăf�X�E�o���[�ɍs���Ă݂��B�Ǝ��̒J�B���̂��킢���O�ɕ�������炸�A���n��������̂��킢����n�Ə�e�͂Ȃ����������Ƃ����A����Ӗ��A�n���A�Ƃ����R�A���ƂĂ����������Ă����Ƃ��낾�B �@�\�㐢�I���A�J���t�H���j�A�B�ɂ�����z��ڎw���Ă�����s�����̒n�ɖ������݁A�������ɂ��ӎ�������Ȃ��悤�ȁA�ߍ��ȏɒǂ����܂ꂽ���Ƃɒ[���Ă���n�����Ƃ����B �@���ہA�l�Ԃ��ӂ��ɐ����ł���Ƃ���ł͂������Ȃ��B����ȂƂ��낾����Ȃ̂��A�l�Ԃ̂����ۂ��Ȋ����Ƃ��A���͊��̂悤�Ȃ��̂����ӎ������������ŁA���炭���̏ꏊ�ɕ����߂��ĒE�o�ł��Ȃ��Ȃ������Ƃ��A�ܐ߂Ɍ��Ă��܂������ȋ��낵����_�X�����̂悤�Ȃ��̂��A�䂪�g�ɔ����Ă����B �@���т₩�ȃ��X�x�K�X�E�X�g���b�v�ɂ���z�e������Ԃ���������Đ��S�L���A��������ȂƂ���ɉ^��ł��ꂽ�K�C�h����́A�����̔��������Ƃɂ���Ȃ��Ɠ��̏�����t���đ���o���悤�ȁA���ɖ��邢���N�̓��{�l�j���������B �@���̒n�ɏZ��ł��łɎl�����I�͌o�߂��Ă���Ƃ������̒j�����A�����ȃf�X�E�o���[���邠���b���Ă��ꂽ�̂����A�Ȃ��Ȃ������̂��Ƃ͌�낤�Ƃ��Ȃ��B���O���狳���Ă���Ȃ��̂��i�܂��A��������Ȃ��c�c���͂͂͂́I�Ƃ�������Ɂj�B �@�ЂƂ����A�����̍��ԂɁA�́A�o�u�����ɐe�̉�Ђ���ςȊz�̎؍�������A��Ɨ��U�ƂȂ�A���������{�ɂ�����A���܂�����_����g�̏�ł��邱�Ƃ�Ƃ茾�̂悤�ɂ��ċ����Ă��ꂽ�B �@����ȃK�C�h����̕s�v�c�Ȉ�ۂ��܂����A���Ɏc���Ă����ԂŁA�A��̔�s�@�̂Ȃ��ł����Ƃ̕��̃G�b�Z�C��ǂ�ł�����A�ŏ��̐���i�͓o��l���ɖ��O��������Ƃ����Ȃ������A�Ƃ����L�q���o�Ă����B�ȒP�ɂ����ƁA�܂������̏����Ă�����̂Ɋm�M�̂悤�Ȃ��̂��͂�����Ƃ͎��ĂȂ��āA�悤�₭���O�����邱�Ƃ��ł��n�߂���i����A�����̊o��̂悤�Ȃ��̂������Ƃ��ł����A�Ƃ����̂��B �@�_�Ɠ_���q����悤�Ȋ����ŁA���̂����͋����Ă��ꂽ�f�X�E�o���[�̓��{�l�K�C�h����̂��킢���Ί炪�A�ӂƓ����悬��A�����Ȃ��Ƃ��Ă��܂���������p����悤�Ȏv���������B �i II �j 2015�N10���� �y137�z�@���̍�Ƃ���i�`����Ƃ��Ă����j�́A���M�̏ꏊ�A�Ƃ������ʒu���̂��̂ɈӖ��������Ă�����悤�ŁA���M�Ɏg�p���钷�N���p�̃p�\�R���̐ݒu�ꏊ���A�t�@�b�N�X�u����̉��ɂ��针�Ԃ���ȃX�y�[�X�ɂȂ��Ă���Ƃ����B�Ȃ��A���̏ꏊ�Ȃ̂��A�Ƃ����������Ȃ��Ƃ͂����ł͖��Ȃ����Ƃɂ���B �@���ہA���̏ꏊ���A�����ւ�厖�ȃ|�C���g�ɂȂ��Ă��܂��Ă��āA���̏ꏊ�����炵�Ăӂ��Ƀf�X�N�̏�Ƀp�\�R����u���Ă��܂�����Ȃ�����A�����Ȃɂ������������Ȃ��ď����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��悤�Ȍ����������B �@����ȃx�X�g�|�W�V�����ł��̓��̎��M�Ɉ��������悤�Ƃ����Ƃ���A����͋N�������B�����܂ŏ����i�߂Ă����ӏ��ɁA�ǂ����Ă����ׂĂ���łȂ��Ƒ����������Ȃ��悤�ȂƂ��낪�o�Ă��Ă��܂��A�܂��A������x�̋����͂��傤�͂����������ȁi�������A�̈Ӂj�A�Ƃ�������������A�܂��Ɉ�i���A�Ƃ����ǖʂ������Ƃ����B���̃^�C�~���O�ŁA�����̓��ォ��A�}�Ƀt�@�b�N�X�̎�M�������̍쓮���ƂƂ��ɁA�v�����g���ꂽ���̂��f���o����Ă����B �@�����ނ�Ɏ�Ɏ�����t�@�b�N�X�ɂ́A�܂��ɂ��ꂩ�璲�ו����K�v�������A�h���s�V���Ȏ���������Ă����B�悭�悭���Ă݂�ƁA����͒S���ҏW�҂��瑗�M���ꂽ���̂ŁA���̓��A�}���قɍs���āA���̎����������炭�i�قɕK�v�ɂȂ邾�낤�A�Ɛ��ǂ�ő��������̂������悤���B����́A�Ȃɂ��̒��ɈႢ�Ȃ��Ǝv�����`����́A���̂܂܁A��C�萬�ɕM��i�߂Ă������Ƃ����B �@���̘b�������āA�Ȃɂ���ȈӖ��ł͂Ȃ��A�n��̑����Ƃ������A�Ӗ���������ƈႤ���AGod bless you�I�ȁu���v�������Ă��܂킴��Ȃ������B���Ƃ��ƁA�`����́A�v���b�g�Ȃǂ����邱�ƂȂ��A�����ʂ�A�ǂ����s�����ȏꏊ����~��Ă�����̂��������L�I�ɏ����Ă����X������������Ƃ��������Ă������A�܂��Ɏ��̖ʖږ��@����G�s�\�[�h�Ƃ��Ĉ�ۂɍ��܂ꂽ�B�������A�����܂ł̜߈ˌ^�̍�Ƃ̕��łȂ��Ă��A�Ȃɂ��傫�Ȃ��̂Ɍ������ď������肵�Ă��銴�o�ɂƂ���邱�Ƃ�����A�Ƃ����b�͔�r�I�悭���ɂ���B�~�X�l���Ă��邤���ɁA�`����̎��M��Ԃ��A���E������ꂽ����̂悤�ȏꏊ�ɂ����v���Ă��Ă��܂����B �i II �j 2015�N9���� �y136�z�@��Ђň�ʓǎ҂̕�����₢���킹�̓d�b�����B�����A75�̏����̕��ŁA�w�����������ɏo�Ă����u���̂��́v�Ƃ������t�̈Ӗ��������Ăق����A�Ƃ������e�������B���̂��́B�u���̂Ƃ������v�Ƃ������������Ӗ��̌��t�����A���̎|���`������ƁA���ł����������B���̗���ŁA���܂܂Ŗ{��ǂ�ł��Ă킩��Ȃ����t�Ȃǂ�����ƁA�������Ђ����肵�Ă����̂����A�ŋ߁A���������������ēǂ߂Ȃ��Ȃ����Ƃ����b�ɂȂ����B���݁A�q���ӂ���͐��l���Ĉ�l��炵�Ƃ������̏����́A���q����Ɂu�C���^�[�l�b�g�Ȃǂ͎g��Ȃ��悤�Ɂv�Ƃ����Ă���Ƃ����B�����̍��\�܂����̔�Q�ɑ������Ƃ�����āA�Ƃ����Ƃ��낪�傫���悤���B�Ȃ̂ŁA���R�A�킩��Ȃ����t�ɏo���킷�ƁA���ׂ���r���v���������A�{�̉��t�̕ҏW���̔ԍ��ɓd�b������̂��Ƃ����B �@���̏����Ƃ̂��Ƃ��ʂ��āA�ӂ��̂��ƂɊ����������B�ЂƂ́A�������g�A�Ȃ�ł�����ł��A�����ɃC���^�[�l�b�g�Œ��ׂĂ킩�����C�ɂȂ��Ă��܂����Ȃ����邱�ƁB�������ɁA�����ɕs�����Ȃ��Ƃ����炩�ɂȂ�A�֗��ł͂���̂����A�������˓I�Ɍ������Ƀ��[�h�Ȃ��ł�����ł��܂����Ƃ������Ă��܂��A���������A�ȑO�قǂɂ͎������Ђ����肵�Ȃ��Ȃ��Ă��邱�ƂɋC�t�����ꂽ�B �@�����ЂƂ́A�l�b�g�Œ��ׂĂ킩�������������A�������Ђ�����A�ЂƂɕ������肵�����Ƃ̂ق����A��ɂȂ��čl����Έ�ۂɗ��܂�Â���A�Ƃ������Ƃ��B���Ƃ��A�́A���̖{��ǂ�ł��āA�悭�킩��Ȃ��Ԃ�̖��O�����̓s�x�A�Ђ��[����ꐶ�������ׂĂ�������̂��Ƃ͍��ł��o���Ă���B�������߂���Ƃ��̎w�Ƀy�[�W���������Ă��銴�G��A�������ɏ����̂Ƃ��낪�g�����܂�ĉ���Ă����l�����ĂȂ������ꂵ���Ȃ�悤�Ȋ��o�́A���ł͂Ȃ��Ȃ����킦�Ȃ����̂��B �@�Ō�ɁB��̏�������A���̎����̂悤�ȏ�Ԃ̏ꍇ�A�������ēd�b�����ĈӖ����ȊO�A�Ȃɂ����Ă͂Ȃ����Ɩ���A�ӂƎv���o�����̂��A�����悤�ȔN��ł��鎩���̐e�ɏ����O�ɓd�q�������v���[���g�������Ƃ������B �@����A���q����A�����ւ�g���₷���d�q�������Ă��炢�A�d�Ă��邱�Ƃ��L���������J�Ȏ莆���ҏW���ɓ͂����B������̂ق����A���낢��Ƌ����Ă����������悤�ȂƂ��������A�����ʂ͂䂢�C���ɂȂ����B �i II �j 2015�N8���� �y135�z�@����n���̖�����ɂӂ��Ɨ���������ہA�v�킸���Q�̐��������Ă��܂����B�����\���N�ň�ۂɎc���Ă����f��̂ЂƂu���A�A��v�̊ēA�A���h���C�E�Y�r���L���c�F�t�̊��S�X���[���Ă����ߍ��{��A����f����Ƃ����̂��B���̏�ɋ����킹���m�l�ɁA�@�����r���A���̊ē̃f�r���[�삪�����Ɏ����̐S�ɍ��܂�Ă���̂��A�����Ƃ����������o�����Ƃ����Ƃ���ŁA���t���o�Ă��Ȃ��Ȃ����B�ǂ��ł��悢�}�t�̂悤�ȃG�s�\�[�h��Ⴂ�o���҂̂ЂƂ肪�B�e��ɖS���Ȃ��Ă��܂��Ă������ƂȂǁA���悻���b�̗v�����班�����ꂽ���Ƃ����v���o���Ȃ��̂��炭�ł���B �@������A�L���͂̌��ނ����������o���Ă�����肾�������A���ɂ����܂ŗ��Ă��܂����̂�……�ƐS�܂���悤�ȋC�����ɂȂ����B�ނ��A����܂ł��A����Ŋς��͂��́u�X�^�[�E�E�H�[�Y�v�̃G�s�\�[�h�P�𐔔N��ɉ����̋@��Ɋς��ۂɂЂƂ̃V�[�����o���Ă��Ȃ��������ƂɋC�t���A���R�Ƃ������Ƃ͂������ɂ������B�����A�����̂Ȃ��ł͐�̉f��̂悤�Ȉ�ۂ̍��܂���Ƃ͂܂������قȂ郌�x���̂��̂������͂����B�Ƃ����킯�ŁA�₩�Ɏ����̂��Ƃ��M�����Ȃ��Ȃ��Ă������́A����܂œǂ�ł��Ĉ�ۂɎc���Ă��鏬���̍[�T�����݂Ɏv���N�����Ă݂��̂����A���ꂪ�܂��A�ǂ��ɂ���Ȃ����������ƂɋC�t���Ă��܂����B����Ȏ����̃��o���ɂ��͂┼���ɂȂ邵���Ȃ���ԂɊׂ肩���Ă����Ƃ��ɁA�ǂ�ł������鏬���̂Ȃ��ŁA����ȓ��e�̈ꕶ�ɏo�������B�H���A������ǂ�ł��鑤�̐S�̂Ȃ��͐₦�����Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�����ꂻ�̒��g�����ԂƂƂ��ɕώ����Ă��܂����̂Ȃ̂��A�ƁB �@�������Ɉ�̏����ł��ǂނ��тɈقȂ��ۂ���������A�ʂ̌��ɖڂ��s���Ă��܂����Ƃ�����̂͂悭�����Ă��邱�Ƃ����A����������ǂ�ł��鎞�Ԃ̂Ȃ��ł��A�s����ȗ���̂悤�Ȃ��͔̂�������������悤�Ɏv����B���ǂ̂Ƃ���A��̍�i�ɑ��āA�����ǂޑ��̑������͂܂��ɐ獷���ʂł���A����l�����ł����悤�ɑ����������C���[�W�̂��̂ł���Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ЂƂ̖{�̌`�ɂȂ��Ă���ƁA�s�ς́A���肵���܂Ƃ܂�Ƃ��čl����ꂪ�������A�v���[���[�̂Ȃ����R�[�h��b�c�Ɠ����ŁA����́A�ǂݎ莟��ł����܂����݂̊o���Ȃ��A�����������A�Ȃ��������̕s�m���ȉ�Ɍ����Ă��Ă��܂�����s�v�c���B �i II �j 2015�N7���� �y134�z�@���̃y�[�W�����ǂ݂��������Ă��鐔���Ȃ����肪�����ǎ҂̕�����u�Ȃ��A���ʓ|�L�����Ȃ��Ƃ��菑���Ă��āA�悭�킩��Ȃ��A�Ȃ�Ƃ��Ȃ�Ȃ��̂��v�Ƃ������w�E�����B����͂��������A�ǂ��������Ƃ��낤�B�Ƃ����킯�ŁA���̋@�ɏ����l���Ă݂��B �@�������{���������n�߂Ă���̗�������U��Ԃ��Ă݂�ƁA�ӂ����Ƃ̕��X�Ƙb������A�ނ炩�畷�����b�������Ȃ�ɍl�����肵�Ă���b�������Ă����ς���ł���B�Ƃ������A���������b�݂̂��ł��邾���ӎ����Ȃ��珑���Ă����C������B���ꂾ���A�ނ炩�甭�M�����b��ȂɁA��X��������������Ă����Ƃ������Ƃł���A�����̕ҏW�����Ă����햡�̂ЂƂ������ɂ���悤�ȋC�����Ă���B �@�������Ȃ���A�i���X�₨���̐ȂȂǂŁA�܂��̂ЂƂ��^���b�Ȃ����Ă����ʂŘb���ɂ��ẮA�ԈႢ�Ȃ����Șb�����Ă��āA������ƂƂ������A���Ȃ�܂�肩�畂���������ɂȂ��Ă��܂��Ă���̂�������Ȃ��i�Ƃ��ǂ��A���̂悭�ʂ��Ƃ̕��Ƃ������傾�ƁA�ׂ̃e�[�u���̂��q���A���炩�ɂւ�Ȋ�����Ă�������`���������肵�Ă���C�z�������邱�Ƃ����邪�A�v�́A����������|�̃��A�N�V�����Ȃ̂��낤�B���_�A���̎�̘b�̎��ɂ́A���������_���������������̂܂܁A�����Ɏ��߂��ꂽ�悤�ȑԂŋ����C���ɑ��Â���ł����肵�Ă���̂ŁA�]�v�Ɋ댯�Ȋ����̋�C��������ɐU��܂��Ă���̂�������Ȃ����j�B�������A������Ȃ��b���������Ă͂��邵�A���ƂłȂ�̘b�����Ă��܂����낤�c�c�Ɠ�����������Ȃ�悤�Ȓp���������g�̏�̘b�����Ă����������̂����A��Ƃ̕��X�Ƃ����ł��Ȃ��ނ��̘b�i���̐l����������i�̘b��A���߂��ēǂ{�̘b�Ƃ��ɂƂǂ܂�Ȃ��A�Ȃ�Ƃ������A���̏����莩�g����v�킸�Ƃ����������łɂ��ݏo�Ă���悤�Ȃ��̂̌�����l�����A�ʂĂ͏���U�镑���܂Łj�������ȈӖ��ł������낷����̂��B �@������A�ǂ����Ă����́u�������낢�����v�����t�ɂ��悤�Ƃ��Ė�N�ɂȂ��Ă��܂��̂����̍��̔����������Ƃ���Ȃ̂����A�����Ƃ̕��H���A�u�ł��A���������̂����t�ɂ����Ƃ���A����͂Ȃ�Ƃ������A�ׂ̂��̂ɂ����ƌ`��ς��Ă��܂���v�B �@���ɖ����B����ł��A���t�ɂ������Ȃ�̂͂Ȃ��Ȃ낤���B �i II �j 2015�N6���� �y133�z�@�����Ƃ��A�����ŏ������L�����Ȃ��悤�ȕ��͂��ł��邾�����������A���̂��߂ɁA���낢��Ǝ��݂Ă���A�Ƃ�����ϋ����[���b�����Ă����B��̓I�ɂ����ƁA�ӎ�������Ƀt���[�g��Ԃɂ��Ă����A�����������Ă���r���ŁA�����̖��ӎ�����������ꕶ�Ȃ�A��A�̕��̘͂A�Ȃ������o�����Ƃ�S�����Ă���Ƃ����̂��i�Ȃ��A����Ȃ��Ƃ��H�@�Ƃ����^��ɂ͍���͐G��Ȃ��ł����B����������ɂ́A���̍��͂������ɒZ������C�����邩��j�B �@����͂ǂ̂悤�ȏ�ԂȂ낤���B�u�C�₷��悤�ȁv�����ŏ����Ă���̂��߂��̂��낤���B�悭�A���e�������Ă���₯�Ƀ��A���Ȗ������邱�Ƃ�����A�Ƃ����b����Ƃ̕��X���玨�ɂ��邱�Ƃ����邪�A����ɂ��Ȃ�߂���ԂȂ낤���B �@�Ƃɂ����A�����ʂ�ӎ������ł����̂�����A���Ƃ������̃��C�e�B���O�E�n�C��Ԃ��������Ă����āA�R���ɃW�����v���A�����̊Ď����瓦��Ă����悤�ȁu��ԑ̌��v�����肾���Ă������ƂɊԈႢ�͂Ȃ��͂����B���̃g�����X��ԂƂ������A�s���̂悤�ȏ�Ԃ����o����Ƃ��K�v�ɂȂ���A���̏�����̕��́A�Â��[�ȂƂ���ŁA����Ƀw�b�h�z�������āA�����܂������������Ȃ��^���Ԃ̂悤�ȂȂ��ŁA�悤�₭���������u��H�v�ɓ��邱�Ƃ��ł���̂��Ƃ����B �@�������Ȃ���A�������������������o�I�Ɏ�����Ă���l�̏��������̂ŁA���������ǂ������������u���L���v��Ԃ̂��̂Ȃ̂��A�ǂݎ�ɂ́A�قƂ�ǂ킩��Ȃ��C������B�����炭�A����́A������̂ЂƂɂ����킩��Ȃ����̂��낤�B����A���炭���Ԃ��o�ƁA���̖{�l�ł����A�ǂ������������`�ŏ����ꂽ���̂Ȃ̂����킩��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����Ƃ������A�ꍇ�ɂ���Ă͂���ȕ��ɂ��ď������Ƃ����L��������ł��܂����Ƃ�����Ƃ����B�悭��Ƃ̕������҃C���^�r���[���āA���C�^�[����̎���ɓ������Ȃ������肷���ʂ����܂ɖڌ�����̂����A����Ȃǂ��A���������ɏ������̂ł͂������Ȃ��A���̎��A���������������ŁA���ƂȂ��Ă͎v���o���Ȃ��A�Ƃ����������������c��Ȃ��̂��낤�B�u�悭�o��l��������ɓ����o���v�Ƃ������t�����ɂ��邪�A����͂�����������A���̂悤�Ȉӎ��I�ȏ������Ƃ邱�Ƃł悤�₭���ǂ蒅����悤�ȁA��Ƃ̕��ɂ͙F��̂悤�ȏu�ԂȂ̂�������Ȃ��B �i II �j 2015�N5���� �y132�z�@�����̕��͂�ǂ�ł��邤���ɁA�����������������ĕʂ̂��Ƃ��l���Ă��܂����Ƃ�����A�Ƃ����b�������O�ɂ����ŏ��������A�ꍇ�ɂ���ẮA�܂������W�̂Ȃ��u���A�����H�v�Ǝv�킸�����Ƀc�b�R�~����ꂽ���Ȃ�悤�ȁA�ꌩ���̊W���Ȃ��A�P�ɏW���͕s���Ȃ̂ł́c�c�Ƌ^���Ă��d���Ȃ��悤�ȃP�[�X���A���͊܂܂�Ă��邱�Ƃ����Ȃ�������Ȃ��B �@�������Ȃ���A����Șb�����s�I�ɂ����Ƃ���ɂ����Ƃ���A���₢��A�����͂����Ƃׂ̂Ƃ���ɂ���̂ł͂Ȃ����A�ƁA�ڂ���E���R��������悤�ȉ��߂����Ă����������̂ŁA�����ɏ��������Ă݂�B���������ɂ́A�������̂ɁA����A�����ꂽ���̎��̂ɁA���������ǂݎ����z��ߋ��̎��Ԏ��ɗU���悤�ȋ@�\����������Ă���̂�����A�����������Ƃ͋N���蓾��Ƃ����̂��B�b���Ă��Ĉ�u�u��H�v�ƂȂ������A�v�́A���������������̂������ꂽ�u�ԁA�ߋ��̂��̂ɂȂ�Ƃ���������ттĂ��邱�ƂɋN�����Ă���Ƃ����B �@�悭�����u��Ƃ��邠��v�̂Ȃ��ɁA�u�L���͂������v���́A�����Ƃ����ƁA�L���̍ו��̕ۑ���Ԃ��f���炵�����̂Ƃ��������̂�����B��ÂɂȂ��čl���Ă݂�Ύ������ł��Ȃ�������A���̌������̂܂����ɖ��ߍ��ނ悤�Ȃ��Ƃ͂���قǂ����ł͂Ȃ����낤���A�ނ���A�I�݂Ɏ��g�̋L����̂Ȃ��ɕ��ꍞ�܂���P�[�X�̂ق������|�I�ɑ����͂����B�����l���Ă݂�ƁA�����ł����u��Ƃ̋L���́v�Ȃ���̂́A���ɂ�����ʂ̋L���͂Ƃ͏����قȂ��Ă��āA�ǂ��炩�Ƃ����ƁA����̏ɉ������L���̎��o�����A�y�т��̉��H�̎d���Ƃ������e�N�j�J���Ȃ��̂Ƃ��čl�����ق����悢�̂�������Ȃ��B�b���������ꂽ���A�����ꂽ���̎��̂��ߋ��������K���������Ă��邱�ƂƁA�i�ǂݎ肪�l����ȏ�Ɂj������ł́u�L���̍ו��v�����Ӗ��̑���Ƃ́A�����W������悤�ȋC������B �@���݂̎��Ԃł��낤�ƁA�����̏o�����������Ă��悤�ƁA���ꂪ�����ꂽ���̂ł���ȏ�A�������u�Ԃ���ߋ������ӂ��ʂɕY���o���A�����炱���A������ǂނƂ������Ƃ́A��z�┽䍂Ƃ������ߋ��̎��Ԃ����Ẵx�N�g����ǂݎ�ɂ������o�̂����ɋ����Ă��܂����Ƃ�����̂�������Ȃ��B �i II �j 2015�N4���� �y131�z�@����~���[�W�V�����̕�����A�쎌����Ƃ��ɁA�ŏ��ɂ܂��t���[�Y�����܂�āA�����ɂ��Ă͂߂�悤�Ɏ����v�������ׂ�Ƃ����n��̗���������āA������O�̂��Ƃ����A��͂�A�����̏������Ƃ͂��������Ⴄ�Ȃ��A�Ƃւ�ȂƂ���Ŋ��S���Ă��܂����B�����̏ꍇ�A���y�����āA�����ɏ悹��悤�ɕ��͂������Ă����A�Ƃ����悤�Șb�͕��������Ƃ��Ȃ����A���ہA�������Ƃ�����A�ƂĂ��������낢�C�����邪�A������Ǝ����I�ȍ앗�̂��̂ɂȂ��Ă��܂��悤�Ɏv���i�����肪�A�@�݂̂����ɂӂ�ӂ��Ȃ���A�L�[�{�[�h���p�`�p�`����Ă���G��z�����邾���ŁA�Ȃ������낢����������j�B �@�������A���̃~���[�W�V�����̕����A�����o���̎��̕����ɂ͐_�o���g���Ƃ����B�����ł��A�����o�����ƂĂ��d�v������Ă��鎖�́A�����ɏq�ׂ�܂ł��Ȃ����A���ꂪ�����Ԃ܂łɎ��s���낵�Ă��銴�������̂������o�Ă���ꍇ�ƁA���Ƃ�����Ǝn�܂��Ă���悤�Ɏv����ꍇ���������肷�邩��s�v�c���B���̂������l���ďo�Ă������̂Ȃ̂ɁA����Ȋ������v�킹���ɂ����Ǝn�܂��Ă�����̂��l�I�ɂ͍D�݂ł���B �����A�Ǝv������A������̕��͂̃��Y���ɏ悹���āA�ǂ�ǂ��������Ă����悤�ȁA�C���t���Η����悤�ɕ���̕��i�����������Ă��������̂悤�ȁB�ŏ��̈ꕶ����A���̈ꕶ���a���o����A�Ƃ������Ƃ��ی��Ȃ��J��Ԃ���ĕ��͂̂��˂肪�����������Ă����B �@�������A�ł���B�ǂ�Ȃɐ��k�ɏ�����Ă���悤�Ɏv���镶�͂��A�����đ����Ă������Ƃ��Ă��A����͕K���������ꂾ���̂��Ƃł͂Ȃ������肷��B�Ⴆ�A���݂ɏ����肪�܂�܂邠��u���b�N���̕��͂���������������Ă��܂����Ƃ���B���̂��ƁA�}���ŁA���J�o���[����悤�ɓ������͂�łƂ��Ƃ��Ă��A�����Ă��̒ʂ�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�����炱���A��x�����ꂽ���̂͂���ȏ�ł��ȉ��ł��Ȃ����A�����ɂ��������̂Ȃ��A��̂��̂Ƃ������������͂��ł��邱�ƂɂȂ�B �@�b���ǂ�ǂ�Ă����Ă��܂����悤�Ɏv�����A�����������Ă�����Ƃɂ́A�t���[�W���Y�t�@�Ƃ܂ł͂����Ȃ��܂ł��A���y�ɂ�����A������Z�b�V�����I�Ȋ��o���������͊܂܂�Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B�����Ɖ��y�́A���̍����ɂ����āA���Ă��Ȃ��Ƃ�������邵�A���Ă���Ƃ��������̂ł���B �i II �j 2015�N3���� �y130�z�@�����O�Ɍ����f��u�C���^�[�X�e���[�v�̂���V�[���������狎��Ȃ��B����ړI����A�F���̔ޕ��֏o��������l���̃}�V���[�E�}�R�m�q�[���A��s���ė��������Ȏ҂�������}�b�g�E�f�C�����̂���f���Ɍ������A�����Ŕނ̗��S�ɑ����B���̂܂܁A�}�R�m�q�[������Ă������^�@��D���A�ނ�̕�͂Ɍ������}�b�g�E�f�C�����B�����ŁA���̃V�[���͕`�����B���^�@���A�[���̂悤�Ȃ��̂��o���ĕ�͂Ɍq���낤�Ƃ���̂����A���ꂪ�Ȃ��Ȃ����܂������Ȃ��B�Ȃ�����������s����B�������ɏł�n�߂��ނ̐S�������킷���̂悤�ɁA�f��͎��X�ɕ�͂Ɍ����ăA�[�����J�`�J�`�Ƃ�邳�܂�`��������B�₪�āA�����ɂ��Ƃ�i�߂悤�Ƃ�����͂��G���[���b�Z�[�W��ǂݎ�����̂��A�ˑR�A��͎͂���B�����āA����ƂƂ��ɁA���^�@���A��u�ɂ��ĕ��ӂ����B �@�����Ŏ��o�I�Ɉӎ�����Ă���悤�Ɏv���̂́A�ē̃N���X�g�t�@�[�E�m�[�������̗p�������_�̑��삾�B���ʂ�������A���^�@�̂Ȃ��̃}�b�g�E�f�C�����̏����ւ����悤�ȕ\���]���āA�ł�Ƃ����C�Ƃ����Ȃ��悤�Ȃ��̂ɕω����A�@���͔����̌����ɓۂ܂�Ă����悤�ȉ��o���܂��l������B�������A�m�[�����͂����������_���̗p���Ȃ��B�����܂ŃJ�����͘��Ղ����_�̖ڐ��ɌŒ肳��A���^�@�̊O�����炻���`�����ƂŁA�}�b�g�E�f�C�����̎ŋ��̈���r�����Ă��܂��B�ނ̏ł��\�͓I�ȏՓ��́A���^�@����͂Ƀ��[�`�����悤�Ƃ���A�[���̃J�`�J�`�Ɣ�������铮���݂̂ɂ���ĕ`����Ă����̂��B���́A�J�`�J�`�ƌJ��Ԃ����l���A���Ă��鑤�ɂ��Ȃ�̋ٔ�����^���Ă����B�Ȃɂ��s���Ȃ��Ƃ��N����X�������O�ȋC�z���A�������Ղ����������猩�邱�ƂŐ��܂�閭�ȃ��A���e�B�[�i�{���炵���j���l�����Ă���悤�Ɏv���̂��B �@���ہA������f��Ƃ������\�̂Ȃ��̏o�����Ƃ͂����A����܂�̋@���ł̓o��l�������̕S�ʑ������Ă��A����͎ŋ������Ă���A�Ƃ����ӎ��Ɋϋq��t���Ă��܂��B�������A�@�̂���������A�Ƃ����f�����̂́A���ۂɂ̓��P�b�g�̑ł��グ���s�f�������Ă����炩�Ȃ悤�ɁA���A���Ȃ��̂Ƃ��Č��鑤�ɍ���Ă���B�����������_�̑���ɂ��{���炵���̋Z�p�́A������ǂ�ł��Ă��Ƃ��ǂ���������̂ŁA�f��Ə����̕\���̎d���̋ߐڐ����������������Ƃ邱�Ƃ��ł���B �i II �j 2015�N2���� �y129�z�@�ŋ߁A�ǂ��������Ȃ��B�ȑO�ɂ���������������Ȃ����A���e��{��ǂރX�s�[�h���Ƃ�ł��Ȃ��x���Ȃ��Ă��܂����B���Ƃ��ƁA�{��ǂނ̂͒x���������A�ŋ߁A���̌X���ɔ��Ԃ��������Ă���C������B�d���Ɏx�Ⴊ�o�郌�x�����B�Ƃ����킯�ŁA�������ӂ���{�⌴�e��ǂ�ł���Ƃ��A�ǂ�ȕ��ɂ��ēǂ�ł���̂��A���������Ă݂邱�Ƃɂ����B �@���Ƃ��A����ȕ��͂̏ꍇ�B���肪����~���[�W�V�����̃��C�u�����Ă��āA���R���Ȃ��܂𗬂����A����ȕ��ɗ��܂����̂́A����Ŕn�������Ă���̂������Ƃ��ȗ����A�Ƃ��������肪�o�Ă���B���̂Ƃ��A�n������𑖂�悤�ȁA���肦�Ȃ����Ƃ��w���悤�Ȓ����̌̎��Ƃ������ۂɂ��肻�����ȁA�Əu�Ԉӎ������ł����B���̂��ƁA���肦�Ȃ����L�������肪�����A�ƘA�z�������A�Ƃ���ƁA���̗܂́A���q����悤�ȁA�����ʂ芴�ӂ̋C�������痈��悤�ȗ܂Ȃ̂ł͂Ȃ����A���̃��C�u�������Ɛ_�X�������̂������ɂ������Ȃ��A�Ƃ�������ɔ]���̘A�����~�܂�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B���R�A���͂�ǂ����Ƃ͂������f����Ă��܂��B �@�܂��A�ʂ̕��͂̏ꍇ�B�o��l���̏��N���O�ŗV��ł��āA�ߏ��̑����痬��Ă���A�J���[�̃X�p�C�V�[�ȍ����A�܂Ȕ��Ń��Y�~�J���ɂ��������ɁA�����������Ɩ�A���낻��ƂɋA�낤���ȁA�Ǝv���V�[���B�C�t���A�������c�����̍��̕��i�ɔ��ł����A�[���̂Ȃ��A�c�n�ł������ڂ����Ă���ƁA���܂��Ăǂ����̕������瓯���t���[�Y����K���Ă���s�A�m�̉��F���������Ă������Ƃ̂Ȃ����S�点�Ă���B�������o�C�G���́u�A���x�X�N�v�Ƃ������K�Ȃ̈�߂��ƌ�N�킩�����̂����A���̂Ȃ�Ƃ��Ȃ������݂ɖ��������̉^�тɕs���ŋ��������Ԃ��ꂻ���ɂȂ�A�m�X�^���W�b�N�ȉ�z�ɂ�������Y���B���̊ԁA���R�̂悤�ɕ��͂�ǂ����Ƃ͈ꎞ��~��]�V�Ȃ������B�������Ė{��ǂނƂ������ƂɊւ��čl�������Ă݂�ƁA���̏�����ǂ�ł��鎩�����܂߂ēǂ�ł���悤�Ȃ��Ƃ�����Ă���ꍇ������ȁA�Ɩ��Ɋ��������Ă��܂����B�Ƃ����킯�ŁA���Ԃɒǂ����Ă���悤�Ɍ��e��{���ǂ�ǂ�ǂ܂Ȃ��Ă͂����Ȃ������̂���Ă��邱�Ƃ́A�����������炷�������\�Ȃ��ƂȂ̂�������Ȃ��B �i II �j 2015�N1���� �y128�z�@�������炭�̂������ɁA�ʋΓr���̓d�Ԃœ�����q�������������B�N�̂���͘Z�\�O�キ�炢�̒j���ŁA������Ă���B���ݍ����Ă���d�Ԃɓr���̉w�������Ă���ނ́A���܂ꂽ����̎e�n�̂悤�Ȋ����ŁA�����ʂ葫�������悤�ɂ��ď�荞��ŗ��邽�߁A���R�A�ڂ̑O�̂ЂƂ͐Ȃ��䂸��̂����A���炭���āA�^�[�~�i���w���߂��A��q���܂�ɂȂ�Ƃɂ킩�ɋr��g�݁A�ړI�̉w�ɓ��������A�Ȃɂ��Ƃ��Ȃ��������̂悤�ɁA�������Ɨ����オ��A�����Ɍg�����܂܁A�m���ȑ��̉^�тœd�Ԃ���~��Ă����̂��B �@���̐l�̘b���A�����Ƃ���ɂ����Ƃ���A����Șb���J�|�[�e�B�̒Z�тœǂ��Ƃ�����Ƃ����B���̂������Z���b���������ǁA�nj�̊������A���������b�ɋ߂����̂�����Ƃ����̂��B �@���̂Ƃ��́A�Ӂ[��A�����Ȃ̂��A�Ǝv���A�b��͕ʂ̂��̂ւƗ���Ă������̂����A�Ȃ�ƂȂ��A���̌�������������Ă��āA�C�ɂȂ��ĉƂ̖{�I�ɂ������u�J�|�[�e�B�Z�яW�v�i�͖��Y��A�����ܕ��Ɋ��j���ς�ς�Ƃ���Ă�����A���Ԃ�A���ꂾ�ȁA�Ƃ����Z�тɓ˂����������B�u�W���[���Y���v�Ƃ������e�p���S�A�T�����x�̏��я����ŁA���e�͈ȉ��̂悤�Ȋ������B �@���肪�u���b�N�����̉��h���ɂ����Ƃ��A�ׂɖڂ��������A�����̕s���R�Ȓj�����Z��ł������A������A�ǂ��A�Ǝp�������Ă��܂��B���ꂩ��A�\�N�o���āA���肪���X�N���̒n���S�ɏ���Ă�����A���������ɍ����Ă����j�̕��e���A�ǂ��݂Ă��ނ̒j���̓�������痧���Əd�Ȃ��Ă݂���B�v�킸���������悤�Ƃ����Ƃ���ŁA�d�Ԃ͉w�ɓ������A�ނ͗��r�ł��������ƍ~��čs���Ă��܂��Ƃ���Řb�͏I���B �@���̘b��ǂݏI������Ƃ��A���́A�ӂ����ȋC�����ɂ�����ꂽ�B�ЂƂ́A�������ǂ͂��̂��̒Z��������܂������o���Ă��Ȃ��������ƂƁA�����ЂƂ́A���̘b���A���̍�Ƃ���ɂ��Ȃ�������A�����炭�ꐶ�A�J�|�[�e�B�́A���̏��я����̂��Ƃ͐S�ɂƂǂ߂邱�Ƃ��Ȃ������ł��낤���Ƃ��B �@���ʓI�ɁA����A���͓d�Ԃ̂Ȃ��Ŗڌ������j���̂��ƂƁA���̒Z�����b�̂��Ƃ��A���炭�͎v���o�����낤���A�J�|�[�e�B�̍�i�Q�̂Ȃ��ł��A�Ƃ�킯�Ĉ�ې[���킯�ł��Ȃ���т������̐S�ɂƂǂ܂��Ă��܂����Ƃ̂ӂ����������v�킴��Ȃ��̂ł���B �i II �j |
|||||||