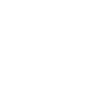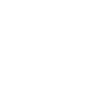人間と猫、それぞれの十年間
丹下健太さんといえば、ご自身と同世代の、不器用で駄目なところもある男性の日常を絶妙なユーモア感覚で描く作家だ。だが四冊目となる単行本『猫の目犬の鼻』の表題作の主人公は、意外なことに一人の女性、そして野良猫たち。彼ら十年間の変化を描くこの中編、著者の頭に最初に浮かんだのはタイトルだったという。
「内容はまったく決めていませんでした。“猫の目”というからにはとりあえず猫は出てくるかな、というくらいで(笑)。以前、野良猫がたくさんいる地域に住んでいて、そこにいつも二匹並んで座っている猫がいたんです。そのうちの一匹の、ぶちっぽい柄の猫の話にしようと思いましたが、さすがにそれだけで話をひとつ書き上げるのは無理で。いつか女の子の話を書きたいとも思っていたので、野良猫と女の子の話を合わせることができるのではないかと考えました」
女性の話を書きたい、という気持ちの後押しをしたのは、とあるテレビ番組だとか。
「何度も同じ人と別れては復縁をするカップルが出ていたんです。自分の周囲を見ていても女性は別れたらさっと引いていく印象があるのに、復縁する人もいる、というのが不思議でした。それで、そういう女の人を書いてみようと思ったんです。それに、一回付き合って別れて復縁するまでの間って、友達でもないし恋人でもない。一体“何期間”になるんだろう、という気持ちもありました」
復縁という過程を書くこともあり、ある程度の期間にわたる話であることは自然と決まった。
「ただ、調べてみたら野良猫の寿命というのは三年から四年くらいしかない。それで、何代かにわたって書いてみても面白いかもしれないと思いました。その間に女の子の成長が書けたらな、と」
地方の街に暮らす根本心美は、中学三年生の夏休み前に同学年の小山一樹から告白される。浮かれつつもどう返事をすべきか迷い、とりあえず「友達から」と言って付き合い始めた彼女。しばし幸せな期間が訪れるが、高校進学と同時期に一樹が引越してしまい、遠距離恋愛になった末、二人は結局別れてしまう。そして経験する大学受験、はじめての一人暮らし、新しい恋人、就職活動。学生生活の終わり頃、心美はSNSを通して一樹と再会する……。
心美は非常に素直で明るい女の子。ただし、ちょっぴり優柔不断だ。
「前半は特に、異性とあまり付き合ったことがなく、はっきりとした自分の意見がなく、流される感じの女の子をイメージしていました。特に取材をしたり経験を活かしたということはなく、すべてこんな感じかな、という想像です。一樹はというと、僕が思う駄目な男の人をイメージしていました」

丹下作品に登場する“駄目男”
実はこれまでの丹下作品には、駄目男に分類される人々が結構登場している。風邪を引いた彼女のお見舞いに大遅刻し、しかも風邪薬と一緒にコンドームを買っていったり(『マイルド生活スーパーライト』)、弟の同棲相手と一時的に同居することになったのに、それを自分の恋人に告げなかったり(『仮り住まい』)。そうした「ちょっと駄目」という描写が絶妙で、読者を笑わせたり、「こいつ、しょうもないな」と、諦念まじりで許容させてしまったり。彼らはみな、駄目だけれども嫌ではない、どこか憎めないところがあった。
「自分ではこれまで駄目男だと思って書いていたつもりはないんですけれど……いや、確かに駄目な部分はありましたが(笑)。ただ、一樹は今までとは毛色の違う駄目男です。これまで書いてきた人たちは“もしかすると自分は駄目なんじゃないか”と思っていた。でも一樹はそうした自覚がなく、むしろちょっと自分に自信があるんです。中学生の頃はそこがよかったのかもしれません。その後彼もそれなりに成長していきますが、根本的なところで何か気づいていない部分がありますね」
本作では他にも“駄目”臭を放つ男性が登場する。心美視点で話が進むだけに、男性の無神経な言動がいかに女心を傷つけているのかもはっきりと伝わってくる。
「特に今回は、クセのある男性を多く登場させたかもしれません。女性になった気持ちで(笑)、こんなことを言われたら嫌だな、という言動をできる限り想像して書きました」
無神経な言動に傷ついたり凹んだりしながら、少しずつ成長していく心美。優柔不断だった彼女も、少しずつ自分で判断できるようになっていく。やがて心美と、一匹の猫が関わりを持った時、彼女はきっぱりと決断を口にするのだ。
「心美が最後に決断する、ということを途中で決めて、そこに向かって物語をなだらかに進めていくことにしました。今まで自分で物事を決められなかった人が、自分で決めて、それを口にするということに意味があるかなと思いました。過去を自分で断ち切るというイメージですね」
中学生の頃から、なにかあると立てた鉛筆が倒れた位置で診断するという、独自の簡単な占いをするクセがあった心美。でも読者にしてみると、その占いをする時には、彼女の心の中には答えがあるように感じられた。自分の意思をはっきりと言えなかった少女が、心の中の決断をしっかりと自覚し、言葉にできるまでが描かれていくのである。

本能に従って生きる猫たち
「猫の目」は心美の中学生時代のあだ名、「犬の鼻」は一樹が犬のように食べ物の匂いを嗅ぐことを表しているが、もちろん前述の通り、猫も登場する。心美と一樹と付き合い始めた頃、心美に「ぶち子」と名付けられた野良猫がいた。ぶち子はいつも一緒にいた弟と離れて行動するようになり、妊娠と出産を繰り返していく。やがて寿命を迎える頃には、ぶち子の娘が妊娠、出産。そうして猫たちは命を繋いでいく。迷いながらゆっくりと歩を進めていく人間と、淡々とおのれの本能に従って生きていく猫たちの姿が対照的。すぐ傍で生活をしながらも、人間と動物がまったく異なる時間、まったく異なる世界観の中で生きていることがよくわかる。
「野良猫を見ていると、かなりはやいサイクルで入れ替わっていますよね。以前家の近所に並んで座っていた二匹の猫は一年くらいの間ずっと見かけていたんですが、寿命が三年くらいだと考えると、自分は彼らの生涯の三分の一を見ていたということに気づきました。人間の寿命で考えてみると何十年かを一緒にいたと思うと、不思議な気分です。もちろん猫にしてみたら一生が人間より短いという感覚はないだろうし、人間と猫のどちらが良いということでもない。ただ、そういうものなんだ、ということが書けたら、と思いました」
身近にいながら、異なる世界で生きている動物同士が、ふと接点を持つ。その様子もなんとも微笑ましい。

自然のものとしての動物
ちなみに丹下作品には必ず動物が関係してくるといっていい。文藝賞を受賞したデビュー作『青色讃歌』は、主人公が同棲相手の彼女から猫探しを頼まれるし、第二作『マイルド生活スーパーライト』でも、犬が登場する場面がある。第三作の『仮り住まい』は、主人公が弟から飼っている蛇の面倒を見てほしいと頼まれるところから話が始まる。今作『猫の目犬の鼻』に収められた「ぱんぱんぱん」は鶏が、「名の前の時間」にも猫が登場している。ちなみに『仮り住まい』の蛇は、「一作目で猫を出して、二作目も似た感じだったので、三作目はあえて嫌いなものを出そうと思った」とのこと(著者と同じく、主人公も大の蛇嫌いである)。
「僕の小説にはあまり自然が出てきませんが、その代わりになる自然のもの、人間と違うものとして動物を出している感覚があります。だから、あまり人間には寄り添わないものとしての動物になりますね。僕自身も十歳になる猫を飼っているんですが、人間と無関係に行動しているところが面白いと思う。特に今回は野良猫の話なので、人間に都合のよい存在にはならないように意識したつもりです」

独特のユーモア感覚
どこかズレた会話のとぼけた味わい、人間の滑稽味を愛らしく見せてしまうユーモアはこれまでの他の作品にも通じることだが、
「昔からお笑いが好きだった、ということが一番大きいですね。関西なので吉本が多いですけれど、お笑いならなんでも好きです」
とはいえ決してギャグに走る作風ではなく、適度に抑制が利いているのも魅力。
「最初の頃は、会話を書いていて楽しくなってくると、延々とやりとりを続けさせていたんです。編集者に何回か“これはやりすぎ”と言われてから、バランスをとるようになりました(笑)」
ではそもそも、丹下さんが小説を書くきっかけは何だったのか。
「小説をきちんと読み始めたのは、二十代の後半くらいから。周りに小説好きが多くて薦められる本を読んでいたんですが、難しいものが多く、なんかよくわからないな、と思いながら読んでいました。その頃一時期東京に住んでいたんですが、彼女と一緒に住もうと思って京都に戻ったら、すぐ振られてしまって。どうしたらいいんだろうと考え、趣味を見つけることにしたんです。小説ならパソコンさえあれば一人ですぐできるし、保坂和志さんの本にも小説は書いてみないとわからないものである、みたいなことが書いてありましたし。ただ、締切などを決めないと続かないだろうと思い、文藝賞に応募することにしました。そうしたら一本目は落ちましたが二本目で受賞できたんです」

日常のことを面白く
それまで文章を書いたことはほぼなかった、というから驚きだ。その後、自身と同世代の男性の日常を描いてきたわけだ。『青色讃歌』は「あれはあれで一応自分にとっての同棲生活の理想型」と言い、『マイルド生活スーパーライト』については「彼女の家に入れてもらえなかったことなど、自分の実体験を誇張して書いている部分があります。僕は風邪のお見舞いにコンドームを買っていったりはしませんが(笑)」。『仮り住まい』は「蛇を中心にした話を書こうと思っていましたが、だんだん同居相手となるみきという女の子のほうが面白くなって。その子の魅力を出したほうがいいな、と考えて書き進めました」。
『猫の目犬の鼻』に収録されている作品でも、「ぱんぱんぱん」は「授業中の教室に鶏が入ってきた、ということを友人から聞いたことがあって。そこから想像を膨らませました」という。これは鶏が闖入した教室での奇妙な風景と、視点人物が一人のクラスメイトについて思いを巡らせるお話。「名の前の時間」は、幼い娘が猫の名前をつけようとしたことを機に、自分の名前の由来について改めて思いを巡らせ、さらには実家であるノートを見つける父親の話。こちらは非常に心温まる(駄目男要素一切なしの)短編であるが、丹下さんらしい人の営みの中の滑稽味も溶け込んでいる。
「身近なことを書こう、というのはずっと思っています。日常とは何かとか、普通とは何かを考えると難しくなりますが、日常の、普通っぽいものの中にある面白さが書けたらいいなと思っているんです」
デビューして七年間で四冊。読者としては、もう少し多く読みたいものだが、
「冊数が少ないとはわかっているんですが、書くのが遅いんです。読書量が少ないことも気になっていて、日々本を読んだりしていて。それでさらに遅くなってしまうんですよね……」
……気長に待ちたいものである。
(文・取材/瀧井朝世) |