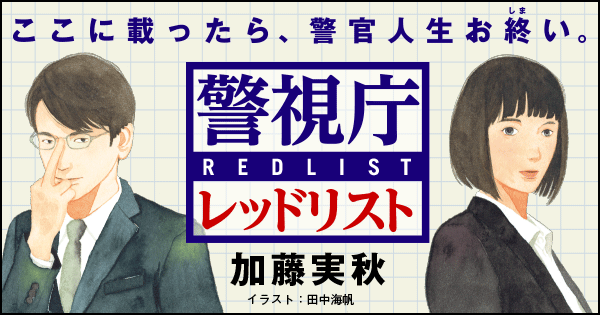〈第7回〉加藤実秋「警視庁レッドリスト」

あやしい男たちと遭遇する。
CASE2 ローン、アローン:借金警察官の涙(3)
6
「あのマンション、築二十年ぐらいですよね」
沈黙を破り、みひろは口を開いた。運転席で資料を読んでいた慎が顔を上げ、フロントガラス越しに前を見た。三十メートルほど離れた場所に、マンションがある。六階建てで戸数は二十ほどだ。
「ええ」
慎が頷き、みひろはさらに言った。
「里見が警察共済組合で組んだ住宅ローンって、三千五百万円でしょう? いくら中古とはいえ、ここは世田谷区。窓の数と大きさからして六十平米ぐらいの2LDKだから、四千五百万円はするはずですよ。どうやって……ああ。親に頭金を出してもらったパターンか」
「また分析ですか」
「いえ。ただの邪推です」
「いずれにしろ、発想と着眼点がいいですね」
淀みなく返答し、慎は書類に目を戻した。微笑んではいるが、内心では発想も着眼点も「どうでも」いいと思っていそうだ。「はあ」と言って助手席で伸びをしたらあくびが出て、みひろは慌てて口を押さえた。
渋谷で慎と会い、里見の行動確認を再開して五日になる。毎日変わる勤務形態とパトロール先に合わせて尾行したが、里見は勤勉そのもの。懲戒処分と罰俸転勤(ばっぽうてんきん)が待っているのはわかっているはずなのに、態度に変化はない。勤務後もやけ酒を飲みに行ったりはせず、まっすぐ分駐所から徒歩二十分のこの自宅マンションに戻っていた。当番明けの今日も午前十時前に帰宅し、今は午後一時だ。
里見の処分を巡って慎に言い渡されたことは、納得はいかないが正論だ。じゃあ、感情や主観だけじゃない真相を突き止めて、と尾行や情報収集をしているが手がかりはない。さっき慎に「今日結果が出なければ、行動確認は終了」と告げられ、これまた納得いかなかったが何も言い返せず、沈黙が流れる車内にエンジンのアイドリングとエアコンの音が流れていた。
「里見はパソコンやカメラ、服をフリマアプリで売っていたんですよね。でも今年の三月から四月のことで、仲間からお金を借りる前。消費者金融などから新たな借金をした形跡もないし、三十万円の出所は謎のままです。じゃあ、家族から? と確認したけど、それもなし。里見は父親も警察官なんですね」
糸口を求め、みひろはバッグからファイルを出した。中には豆田からもらった資料と里見の身上調査票の他に、この五日間で集めた情報が収められている。
「ええ。群馬県警交通部の調査官、警部です。祖父も元警察官なので、いわゆる警察一家ですね」
周囲を確認し、慎が言う。閑静な住宅街なので長時間駐車していると不審に思われるため、時々車を出しては前と違う場所に停まる、を繰り返している。顔を上げ、みひろは問うた。
「そのパターン、多いですよね。自営業の跡取りとかならわかりますけど、なんでわざわざ親と同じ職業に就くんでしょう」
「祖父と父の背中を見て育ち、同じような警察官になりたいと入庁した、というような話をよく聞きます。親や警察の採用担当者に勧められて、という人もいますね。職員の家族なら身元は確かですし、職場結婚と同じでしょう」
「身元ねえ。家族を尊敬して憧れて、ってすごく素敵だと思いますけど、息が詰まったりしないのかなあ。比較されるだろうし、仕事ぶりは筒抜けでしょう?」
「比較されるのはモチベーションになるし、筒抜けになってまずいことをしなければいいのでは?」
間髪を入れず、慎が問い返してきた。また正論か。しかもこっちが、「ちょっと変なこと言ってる」みたいな顔してるし。うんざりしつつも口には出せず、みひろは返事の代わりに問いかけた。
「ひょっとして室長も、警察一家出身ですか?」
「いえ。違います」
目をそらし、慎は前を向いた。相手を遮断するような口調は初めてではないが、どこか頑ななものを感じ、みひろは意外に思う。が、すぐに「警察大好きな人だし、気のせいか。ていうか、話の流れで訊いただけでどうでもいいし」と思い直してファイルに視線を戻した。
二時間後、マンションのエントランスから里見が出て来た。隣にはチュニックワンピースにレギンス、素足にサンダル姿の小柄でぽっちゃりした女。妻の亜子(あこ)、二十五歳だ。買い物に行くらしく、亜子は花柄のエコバッグを提げている。二人が通りを反対側に歩きだすのを確認し、みひろたちは車を降りた。距離を空け、尾行を開始する。今日も晴天で日射しは強く、みひろはスーツのジャケットを脱いだ。
五分ほど歩くと、亜子は里見の腕に手をからめた。自分より三十センチ近く背の高い里見を甘えた眼差しで見上げ、話しかける。Tシャツにジーンズ、スニーカーという恰好の里見も少し眠たそうで後頭部の髪の寝ぐせはひどいが、笑顔で応えていた。
「里見はともかく、奥さんの屈託のなさはすごいですね。新婚早々旦那さんが左遷されて、定年まで昇進できなくなっちゃうんですよ。よくあんな風に笑えるなあ」
慎の後を付いて住宅の塀や路上駐車している車の陰に隠れて歩きながら、みひろは言った。前方を注視しつつ、慎が返す。
「里見亜子も元警察官ですから。懲戒処分にならずとも左遷されることはあるし、覚悟の上だったのでは? 職場結婚ならではですね」
また職場結婚を肯定? 室長って実は既婚者で、奥さんは警察官? いや、正論に基づいた教育的指導ってやつか。やっぱり警察が大好きなんだな。再びうんざりしながらも気持ちを立て直し、みひろは返した。
「でも、あの奥さんの様子は覚悟って感じじゃ……ひょっとして、何も知らないんじゃないですか? 里見は処分のことも借金のことも、奥さんに話してないのかも」
みひろが閃いたことを言葉にしている間に、里見たちは住宅街から商店街に出た。二人が通り沿いのスーパーマーケットに入ったので、みひろたちも続いた。
「なぜ話していないんでしょう?」
出入口に積まれたプラスチック製のカゴの一つを手に取り、慎は訊ねた。エアコンの冷気にほっとしながらみひろもカゴを取り、
「心配をかけたくない、または失望されたくない。あるいは、他に話せない理由があるとか」
と答えた。弁当と惣菜の売り場に行き、商品をカゴに入れる。もし里見に見つかっても、「買い物に来て偶然会った」と装えるからだ。みひろも慎もおにぎりではなく、サンドイッチやハンバーガーなどを手に取ってしまうのはパン好きゆえだ。
「理由とは?」
「私にばっかり答えさせないで、室長も考えて下さいよ」
口を尖らせて訴えたみひろに慎は、
「僕は予想や憶測でものを言わない主義だと、先日言ったはずですが」
と平然と告げる。うんざりを通り越してヤケになり、「でしたね~」と笑顔で返し、みひろは続けた。
「わかりませんけど、借金の理由が結婚や生活費なら、奥さんが知らないのは不自然ですよね……そう言えば、奥さんの親も警察官ですね。お父さんは警視で第八方面の副本部長」
「第八方面?」
飲み物の棚に伸ばした手を止め、慎が振り向いた。第八方面は昭島(あきしま)市、立川(たちかわ)市、府中(ふちゅう)市、武蔵野(むさしの)市、調布(ちょうふ)市など多摩(たま)地域中部の警察署の担当だ。警視庁が区分する各方面には「本面本部」という拠点が設置されていて、第八方面は立川署の近くにある。トップの方面本部長は警視長か警視正で、ほとんどがいわゆるキャリア組だ。
「ええ。違ったかな」
戸惑い、バッグから資料を出して確認しようとしたみひろを、慎は手を上げて止めた。
「いえ、違っていません。その通りです」
「両家とも父親は警察官だけど、新郎側は道府県警察の警部で新婦側は本庁の警視。格差というか、新郎側は複雑そう。でも、里見が挙式前に表彰されたのはラッキーでしたね。披露宴の新郎新婦のプロフィール紹介で、ここぞとばかりにアピールしたんだろうな」
「そうですね」
相づちを打った慎だが、どこか上の空だ。怪訝に思い白く整った横顔を見ると、慎はすぐそれに気づき、棚からミネラルウォーターを取ってカゴに入れた。
「里見を捜しに行きましょう。恐らく生鮮食品売り場です」
言うが早いか、通路を進み出す。「はい」と頷いてみひろも棚から缶コーヒーを取り、後に続いた。