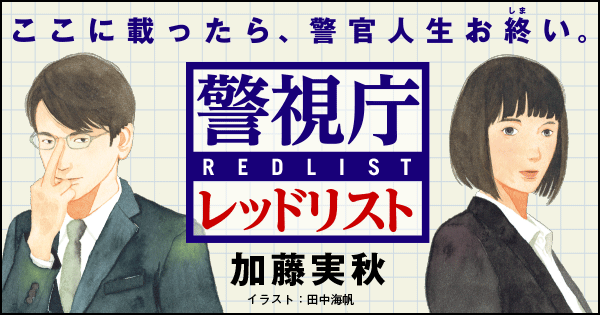〈第2回〉加藤実秋「警視庁レッドリスト」

身内の警察官を調査する
新部署での仕事がはじまる。
CASE1 赤文字リスト:退路を断たれた二人(2)
4
ロッカールームで私服に着替え、慎が運転する車で本庁を出た。
「異動先ではスーツ」って言われたけど、制服の方が面倒がなくてよかったな。そんなことを考えながら、助手席で身につけたライトグレーのジャケットの襟やスカートの裾を整えていると、慎が口を開いた。
「調査対象者は日本橋(にほんばし)署交通課交通総務係の黒須文明(くろすふみあき)巡査部長、三十九歳。既婚者でありながら、署内の女性と交際している疑いがあります」
「不倫ですか。今時珍しくもないし、職務に支障を来してるとかじゃなければ、処分する必要はないと思いますけど」
「必要はあります。不倫は警察職員の『懲戒処分の指針』内の『その他の規律違反関係』における『公務の信用を失墜するような不相応な借財、不適切な異性交際等の不健全な生活態度をとること』に該当し、戒告処分の対象です。ちなみに令和元年中に懲戒処分となった警察職員は、二四三名。その事由のトップが異性関係で、合計八十名。八名が免職になっています」
ハンドルを握り、フロントガラス越しに前を見たまま慎は語った。抑揚のない早口な上に漢字と数字ばかりなので話が頭に入って来ず、みひろは「はあ」とだけ返した。慎が続ける。
「当然ながら、警察官は公務員です。原則的に解雇されることはなく、給与も安定している。一方でその給与と活動資金は国民の血税で賄われており、職務遂行において不適切な行為を行った場合は厳しい処分が下されます」
「それはわかります。でも、『職務遂行において不適切』の基準はなんなの? って──すみません。出過ぎたことを言いました」
鷲尾とのやり取りと季節外れの人事異動を思い出し、みひろは話を打ち切って視線を前に戻した。車内に沈黙が流れ、叱られるか嫌みを言われるかと身構えた矢先、ふっと笑う声がした。反射的に、みひろは横を見た。慎は口角を上げて微笑んでいる。
「三雲さんは民間企業出身でしたね。なぜ警視庁に?」
「大学で就活に失敗して、フリーターをしていたんです。あちこちで働いたんですけど、その一つが通販会社のカスタマーセンターのオペレーターで、苦情と質問に対応しているうちにお客様のグチや悩みも聞くようになりました。お年寄りとか、『三雲さんを指名で』って電話をくれるようになったんですけど、会社に『人生相談の窓口じゃない』ってクビにされちゃって。どうしようと思っていたら、どこかで私のことを聞いたらしい警察の人が『職員向けの電話相談員をやらないか』って誘ってくれたんです。働きだして、間もなく一年になります」
これまでに何度もした説明なので、すらすらと話せる。警視庁が新卒以外で採用するのは基本的に化学や財務、コンピュータ等の専門知識や資格を持つ者だけで、みひろは異例だ。「とは言っても心理学とかカウンセリングの勉強した訳じゃないし、なんの資格も持っていないんです。だからよく『なんで?』って訊かれるんですけど、『誘われたから』としか答えられないんですよね」
みひろがそう続けると前方の信号が赤になり、慎は車を停めた。車は東京駅の八重洲口に差しかかっている。スーツ姿のサラリーマンやキャリーバッグを引いた老夫婦などが歩道を行き来し、傘を手にしている人も多い。空には灰色の雲が立ちこめ、間もなく東京も梅雨入りするはずだ。
微笑んだまま、慎は返した。
「知識や資格があるからといって、的確なアドバイスができるとは限りません。相手の顔が見えない電話相談なら、なおさらです。三雲さんには、人の話を聞いて心に寄り添う才能があるんでしょう。調査の職務に不安があるかもしれませんが、きっとその才能が役に立ちますよ」
「ありがとうございます」
みひろが会釈すると、慎は頷いてハンドルを握り直した。
阿久津室長って見た目はいかにもだけど、中身は思ってたのと違うな。戸惑いながらも、少しだけ気が楽になった。
5
日本橋署は、日本橋人形町(にんぎょうちょう)の地下鉄水天宮前駅の近くにあった。駐車場に車を止め、鉄筋四階建ての古い署に入る。一階の受付で慎が名乗ると、すぐに奥の署長室に通された。
「伺っておりますよ。職場環境改善推進室は、持井首席監察官の肝いりで設立されたとか……持井さんはお元気ですか?」
満面の笑みを真顔に戻して訊ね、署長の滝見(たきみ)は応接セットのソファから身を乗り出した。
「はい。お陰様で」
向かいのソファに座った慎が頷くと署長は、
「それはなにより。よろしくお伝え下さい」
と満足そうに返し、ソファの背もたれに小柄小太りな体を預けた。歳は五十過ぎだろうか。隣には中背で痩せ型の交通課長の古屋(ふるや)が座り、その脇には大柄で角刈りの警務課長の梅谷(うめたに)が立っている。歳はどちらも四十代前半か。三人とも制服姿だが、滝見だけが濃紺のスーツにネクタイの冬服で、他の二人は肩章付きのスカイブルーのシャツに濃紺のスラックスという夏服だ。
「本庁または所轄署の中から一部署を無作為に選んで聞き取り調査を行い、よりよい職場環境づくりに役立てます。人事一課の調査と言われると緊張したり、不安になったりする職員も多いと思いますが、我々の目的は、それぞれの職場の状況を把握することです。リラックスして質問に答えてもらい、希望や意見があれば聞かせて下さい。もちろん、調査結果は本来の目的のためだけに使用し、人事には反映されません」
流れるような口調で、慎は古屋に語りかけた。「その通りです」の意思表示のつもりでみひろも笑みを作り、向かいを見る。調査対象者及び周辺職員に対しての表向きの説明と接し方は、ここに来る車の中で慎に指示された。
「わかりました。調査に協力するように、課員に伝えます」
そう応えた古屋を振り向き、滝見が言う。
「阿久津室長は、持井さんの元部下で人事一課長の信頼も厚かった人だ。きみたちも学べることが多いはずだぞ」
持井や人事一課長のありがたさを強調するのに夢中で、慎に対しての「元部下」「信頼も厚かった」発言には気づいていない様子だ。
地域警察の「顔」とも言える署長の職責は重く、経歴・人格ともに優れた者でなくてはならない。ゆえに候補になった時点で人事一課の監察の対象となり、尾行や張り込みなどを含めた厳しい行動確認が行われる。これをクリアして署長に就任しても、職務中の行動は配属先の警察署員によって逐一チェックされ、人事一課監察係に報告される。つまり警察署長にとって監察係は畏怖の念を抱き、配慮する相手なのだ。
組織内のそういう構造は知識としては頭にあったみひろだが、直接的な言動を目の当たりにするのは初めてで、「本当なんだ」と物珍しいのと同時にしらけた気持ちになった。それとは別に慎の反応が気になって横目で見ると、整った白い顔は古屋に向けられたままで表情に変化はない。
「それに、うちの交通課は模範的な職員ばかりだ。誰になにを聞いてもらっても、心配ないだろう」
滝見はさらに言い、古屋は首を大きく縦に振った。
「それはもう……調査には協力しますので、なんでもおっしゃって下さい」
「私の方にも、本庁の警務部から連絡がありました。お役に立てることがあればどうぞ」
ソファの脇の梅谷も口を開き、慎とみひろに会釈をする。慎とともに会釈を返し、みひろが「ありがとうございます」と言うと滝見がこちらを見た。
「あなた、三雲さんでしたっけ? 大抜擢だと聞いているし、期待していますよ。こういうフレッシュな人材を起用するのも、さすがは持井さんだな」
最後のワンフレーズは独り言のように言い、滝見は顎を上げて笑った。古屋と梅谷も笑ったが、内心では慎とみひろの来署に戸惑い、煙たく思っているのは明らかだ。
「フレッシュな人材」。オヤジ臭い、ていうか死語。突っ込んでうんざりしつつ、なるほど、これからはこういう反応をされるのか、とみひろは思った。