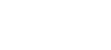昨年7月より募集を開始した
第1回日本おいしい小説大賞
(協賛:キッコーマン株式会社
神姫バス株式会社 日本 味の宿/
主催:小学館)は、
総応募数160作の中から、
2度の選考を経て、
4作の最終候補作が選出されました。
選考委員の山本一力氏、柏井壽氏、
小山薫堂氏による最終選考会で、
さまざまな議論が重ねられた結果、
受賞作が決定いたしました。
「七度洗えば、こいの味」
古矢永塔子
「氷と蜜」
佐久そるん
「ハツコイ・ウェーブ!」
氷月あや
「殻割る音」
深町 汐

私が小説を書き始めたのは、娘とのふとした会話がきっかけでした。「お母さんの将来の夢は?」という問いに「お母さんはもう大人だから」と返した私に対し、娘はひとこと「大人は夢を見ちゃいけないの?」と不思議そうに言ったのです。その日から、毎日少しずつではありますが物語を書き続け、夢を追い続けてきました。
今回、賞の創設の言葉にありました『三十代から五十代の女性は食にまつわる物語を求めている』という部分を読み、ならば三十代の自分が今一番読みたい物語を書いてみよう、と思い立ちました。
特別なご馳走ではない、日常のなかにある料理。調理をしながら込められた作り手の思いと、受け手が味わう苦みや甘み、そこから自然とこぼれる涙と笑い。できることならいつまででも書きつづけてゆきたい、愛おしい物語になりました。
最後になりますが、選考委員の先生方、審査に携わって下さった全ての方々と、執筆中の私を応援し支えて下さった皆様に、心から御礼申し上げます。

果たして「おいしい小説」という限られた枠組みの内で、応募が期待できるのか。
まったくの杞憂だったと、締切期日後に安堵した。最終候補四作は佳作揃いだ。
どれも視点と着想がいい。
今後の精進次第では、次回の大賞に届くやも、との期待も抱かせてもらえた。
「七度洗えば、こいの味」
満票を得ての大賞受賞となった。
本賞は食がテーマの小説募集だが、味覚を競うものではない。
本作はこのことを実証してくれた。
人間が主役のドラマが、きちんと描かれている。料理はあくまでも、物語進行の小道具という位置に徹している。
主人公が容姿を隠すマスク姿なのは、本作の肝をなしている。
当人が隠したいことは、個々に異なる。が、だれしも隠したい事柄を、内に秘めているものだろう。
成長し、時期いたれば、マスクを外して素をさらせる。こころの深淵の動きを、作者は物語のなかで巧みに描写してくれた。
主人公を筆頭に、魅力ある多数の人物を配してくれた筆力が、大賞を射止めた。
「ハツコイ・ウェーブ!」
「食」と「ドラマ」を重ねれば、郷土色が濃厚になる。本作はそれが際だっていた。作者が描く五島からは、写真など見ずとも美しき景観を想起させられた。
魚をさばくのも、ジビエのシカをさばくのも同じだと作者は描く。その感覚は、五島に暮らす者が占有できる斬新さだろう。
筆力ある作者だ。次回に期待する。
「氷と蜜」
受賞には至らなかったが、脳髄を激しく刺激された一作だった。本作を読んだことで、数度もかき氷を食べに出向かされた。
本作に投じられたかき氷への情熱が、果たして次回はなにに向かうのかと、選考会で話題になった。
惜しまれるのは文章の精度・密度にばらつきがあること。念入りに推敲を重ねて、作品のレベルを向上させていただきたい。
「殻割る音」
本作執筆に際し、作者はさまざま取材を重ねられたのではないか。作中からも取材密度のほどがうかがわれた。
惜しむらくは主人公から感じられるリアリティーが希薄だったことだ。
現実と、小説のリアリティーとは別物だ。
いかに「これが今日的」だと提示されても、読者が違和感を覚えては失敗だ。
そんなわけはないだろうと言いつつも、つい作品世界に引きこまれるのが、小説のリアリティーだ。
このことに留意し、次作に臨んでいただきたい。

応募される作者は、おいしい小説、という言葉をどうとらえるか。どんな作品が集まるのか。期待と不安が交錯するなか、最終選考に残った四作品を読んで、期待どおりと、期待はずれが相半ばしました。
期待どおりだったのは、小説に登場する〈食〉がしごく一般的なもので、マニアックな高級食材の話などが出てこなかったことです。もう一方で期待外れだったのは、ある程度、齢を重ねた人の食への思いをテーマにした小説がなかったことです。
偶然か必然かは分かりませんが、四作品のうち三つの作品に小学校高学年の児童が登場し、重要な役割を演じています。
たしかに〈食〉についての、子どものころの体験は、そののちの味覚形成は言うに及ばず、長じての食生活に与える影響は少なくありません。しかしながらそれは、おとなになってから、むかしの記憶をたどることで蘇えるものであって、幼少時に強く意識して食べるのは、きわめて稀なことだと思います。
子どもに込み入った〈食〉を語らせるのは無理があります。
「ハツコイ・ウェーブ!」がその典型でしょうか。離島を舞台にしているところや、食の本質を突くくだりなどは、いい味を出していると思いますが、それを語るのがふたりの子ども、というところがいかにも惜しいと思います。登場人物の名がカタカナになっているのも、リアリティを薄めているように思います。
「殻割る音」もまた小学校六年生が主人公です。小学生が街で出会った同級生に、ケーキを買ってプレゼントするのも不自然な気がしますし、小学生が「これまで食べたスクランブルエッグでベストスリーに入る」と言うのも違和感があります。ある程度のファンタジーはいいのですが、あまりに現実離れしていると、物語に入り込めません。
「氷と蜜」は冒頭から、マニアックな、かき氷の話が延々と続き、かき氷のファンでなければ、読み進むのに苦労します。ブームになっている〈食〉をテーマにすると普遍性がなくなるのではと危惧します。
「七度洗えば、こいの味」ですが、最初は醜悪な顔だと思わせておいて、転換させるのは秀逸です。夫が発信するSNS。運動会の祖母の弁当。リアルな描写もよくできています。 ただ、主人公の女性が恋心を抱く相手の老人との年齢差が気になります。いくらなんでも、ここまでの恋愛感情は起こらないだろうと思ってしまうのですが。
老人と出会ったことで、ひとり立ちできるようになった主人公が、淡い恋心を抱き、それを自問するくらいでおさめておいたほうが、読後の余韻が残るように思います。
最終選考に残った四作品のなかでは、この作品がもっとも大賞にふさわしい小説でした。

審査にあたり、「おいしい小説大賞」というユニークな賞がどうすれば世の中に広まるのか、ブランド価値が上がるのかを考えました。受賞作がドラマや映画などで映像化されて、より注目を集められればと思い、その原作探しをするつもりで今回は読ませていただきました。
「ハツコイ・ウェーブ!」 五島列島の雰囲気や魅力、優しさが伝わってきて、世界観もよくまとまっていました。主人公レンの成長の物語としてわかりやすく、子どもたちのまっすぐな描き方にも好感が持てます。しかし、「おいしい小説」の視点で見ると「食」のポイントが薄く、無理やりな箇所も多かった印象です。食という必然性がなくても成立する題材なので、五島列島を舞台にした心のぬくもりを伝える作品を、改めて書かれてみてはいかがでしょうか。
「殻割る音」 タイトルを読んでいちばん期待した作品でした。料理を主役とした物語で、描写も良く、「おいしい小説」のテーマにも合っていました。気になったのが主人公の年齢です。小学校六年生の少女の口から大切なことを語らせるのに、やや無理を感じました。
「氷と蜜」 この小説大賞だからこそ出会えるような作品でした。「世界初のかき氷エンターテインメント」としてユニークで面白かったです。ただ、小説というよりは漫画のストーリーとして楽しむような感覚でした。漫画原作として書き直せば、人気が出るかもしれません。しかし、今回の最終候補者のなかで、もっとも食に対する考察や知識は深く、何より作者の食への愛を感じました。ぜひ、「かき氷漫画」を世に送り出してほしいです。
「七度洗えば、こいの味」 設定の作り方や展開の持って行き方が上手く、映像化してもシーンを作りやすい、視聴者を引き付けるような構成になっていると思います。気になったのが、ここまで恋愛の物語にする必要があったのかということ。「七度洗えば〜」のタイトルに振り回されているようでもあり、二十八歳の主人公が七十歳を過ぎた男性に果たして恋心を抱くだろうか? と思いました(山本一力先生は「恋はするんだよ」と力説されていましたが……)。そして、主人公の夫に個性をつける工夫があれば、より深みが出たと思います。とはいえ、今回の応募作の中では秀逸で、満場一致で受賞作に決まりました。きっと映像化のオファーもくると思うのでそのときを楽しみにしています。稀代の美食家・ブリア゠サヴァランの名言に「君がどんなものを食べているかを言ってみたまえ。君がどんな人間かを言い当ててみせよう」とあるように、今回の審査を通して、あらためて食とは「人をつくるもの」だと思いました。だからこそ、あまり若い年齢の人を主人公にするのは、おすすめしません。ただ食べ物が出てくるのではなく、食べ物によってつくられた人間の物語と出会えることに、来年は一層期待しています。