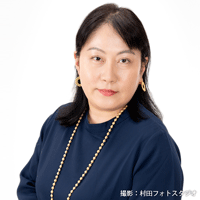インタビュー 河﨑秋子さん 『肉弾』
主人公のような人なら、熊と闘って死んでやる、
という気持ちになるのでは。
北海道の羊飼いであり、作家である河﨑秋子さんの待望の第二作が出た。『肉弾』は、都会に暮らす青年が北海道の山中で熊に遭遇するという、絶体絶命の場面が描かれる。この緊迫した物語は、どのように生まれたのか。
北の山中で熊に遭遇する親子
河﨑秋子さんの職業は作家であり、羊飼いだ。大学卒業後にニュージーランドで緬羊飼育技術を1年間学んだあと、北海道で酪農を営む自宅で緬羊の飼育・出荷をしている。朝は四~五時に起き、夜七~八時まで働く生活のなか、二〇一二年に『東陬遺事』で北海道新聞文学賞(創作・評論部門)受賞。二〇一四年に『颶風の王』で三浦綾子文学賞を受賞した。雪洞に馬と閉じ込められ、生き延びるために壮絶な体験をした女性から命を受け継いでいく家族と馬たちのこの物語は、受賞後刊行されると大変な評判となった。
新作『肉弾』は、現代が舞台だ。主人公はかつて挫折を味わい、いまは大学に行かず引きこもっている青年、貴美也。豪放な父親に反発をおぼえながらも、彼の庇護のもとで生活していたところ、狩猟好きの父親は彼を北海道での狩猟に連れ出す。獲物は鹿のはずだったが、飽き足らない父は、立ち入り禁止の鳥獣保護区に分け入り、熊を狙おうとする。しかし、実際に熊に襲われた時、彼らは──。
「熊の話を書いてみたいと思ったんです。熊と相対するのは誰にするか考えた時、鉄砲撃ちやマタギの血を引く人間にしても物語は成立しますが、そうではなく、熊とはまったく縁のない人間にしたほうが、熊や自然の恐ろしさを書けるのではないかなと」
主人公、貴美也を「甘ったれ」という河﨑さん。
「ニートなのにお金を出してくれる父親にグダグダ言いますよね。大人の立場からすればひっぱたいて小一時間説教したい(笑)。書き手の自分とはかなりかけはなれた人間として設定しています」
また、仕事では成功を収めているが再婚を繰り返し、何事も豪快な父親については、
「貴美也に近い年代の人が読めば“なんだこの父親は”となるだろうし、大人の立場からすれば、この父親はとんでもないけれども、それでも案外親として息子を案じているように見えると思います」
影響しあう人間と動物たち
北海道で熊といえば、吉村昭氏が『羆嵐』に書いたように、羆が集落を襲って何人もの命を奪ったという実際の事件もあった。河﨑さんにとっても、熊はそこまで遠い存在ではない。
「うちの畑の周りに熊の糞があったり、牧草ロールに熊の爪の跡が残されたりもしています。私もジョギングしていた時、二~三〇〇メートル先に黒くてモフモフしていて尻尾のない犬のようなものが横断していくのを見たことがあって。今思えばあれは熊でした。それくらい熊と人間はそばで暮らしているけれども、接触することは少ないんです。接触したとしても、死亡例は数年に一度のレベル。熊としても人間と接触するのは嫌なんだと思います。ただ、一回人間の味を覚えると、人は脂肪分が高いし掴んで食べやすいので、気に入って『羆嵐』の状態になるわけです」
無断で分け入った自然の中で、突然至近距離で熊に遭遇した父子。逃げる間もなく父は襲われ腹を抉られ、息子はひとり死に物狂いで逃げる。この様子が迫力満点に描写されて読者をも震え上がらせる。彼らを襲った熊がどういう生い立ちで、現在どのような状態かも描かれるため、状況に説得力が増す。
「閉鎖空間の中で熊がどういう状態になるのかはもちろんフィクションですが、現実に忠実にあるように心掛けて作りました」
本作には、人間と熊以外にも、重要な役割を果たす存在がいる。それが野犬たちだ。人間に棄てられ、あるいは人間の支配から逃げ出してこの山中で群れをなして暮らす彼らのボスは、オオカミ犬の血を引いた雌。幼い頃にきちんと訓練を受けさせなかったため、大きく成長した後もよく吠え、力が強く、いうことをきかない彼女を持て余した飼い主が捨てたのだ。彼女が率いる集団が、貴美也たちや熊に遭遇する。
「熊と人間が一対一で向き合う時に、さらに平行した立場にいる集団をひとつ出したいというのと、山の中に人間に影響され棄てられた存在があるということを書きたい、という気持ちがありました」
実際に野生化した犬は少なくないという。
「特に引っ越しの多い春先、犬を置いていく飼い主が多いんです。そうした犬たちが集団で群れて、畑で生まれた子牛を襲ったりするので役場に連絡して駆除してもらう。可哀そうですが、農家としては、そうは言っていられないことなんです」
人間と、人間によって生活圏をおいやられた熊と、古から人間に従属してきたはずの犬。三者が出くわした時、何が起きるのか。
「『颶風の王』を書いた時、前半で馬の経済動物である側面をクローズアップし、後半で野生に戻っていく姿を書きました。この新作では、家畜であった犬が人間の手から離れて生息した時にどうなるかをシミュレーションしています」
一人逃れる身になった貴美也とボス犬の間にほのかな意思疎通の兆しが見える。
「犬は人間と共生してきた生き物。たとえば何代も飼われている牧羊犬を見ていると、遺伝子は残るのだなという感じがします。もちろん人間に従順で命令をよく聞く血筋を残しているからそうなるんですが。今回の本に出てくる女ボスは使役犬というよりはオオカミ犬ですけれど、犬はボスの存在を重んじる。自分がボスとして立つし、人間をボスとして認識して立つこともあるわけです」
犬の集団の中には旅行客がリードから離した瞬間に逃げてきたチワワもいる。
「リードを離してしまう旅行客っているんですよ。でも、目を離した瞬間に犬がエキノコックスに感染した鼠を食べたりしたら、本州に病原を持ち帰ってしまうことになりますので気をつけてください」
本作には、そうした現実的なエピソードもたっぷり盛り込まれる。道路に撒く融雪剤はミネラル分を含んでおり、鹿にとって“サプリメント”であるため、彼らはそれを舐めに道路に出てくる、というのも意外な事実。
「物語の中の、そのために融雪剤に毒を混ぜるという部分はフィクションですけれども。他にもレールの鉄分を舐めるために鹿が線路に寄ってきて轢かれる、ということも多いです。自分が汽車に乗っている時に鹿と接触して停まると腹が立ちますが、鹿にしてみればそこに鉄分があるから来るんですよね。そうやって人間と動物は何らかの影響を及ぼしあっているんです」
今、貴美也が置かれている状況も、人間がこの北の地を開拓し、動物たちと影響を及ぼしあった結果だ。それにしても、「甘ったれ」だった彼が、少しずつ変化し、熊との対決を決意するさまも読みどころだ。
「こういう人物が山の中に放り込まれ、窮地に立たされて、逆ギレしたような状態になって熊に向かっていく、という話にすることは決めていました。そこにどれだけ説得力を持たせられるかが大変で。後から過去のエピソードなどを加えて、貴美也の人物像を肉付けしました。ただ、人間は案外火事場の馬鹿力が出ると思うんです。これが妻子持ちだったり社会的に守らねばならない立場のある人だったりすれば、熊と闘うよりも山から出ることを第一に考えるはず。でも彼は人生投げやりで、自分には将来がないと思い込んでいる。しかも、自分を保護してくれる父親を亡くしてしまったばかり。そういう人なら、熊と闘って死んでやる、という気持ちになるのではないかと」
熊対人間対犬。この三つ巴は最終的にどのような決着を見るのか。河﨑さんは、「バッドエンドとして読んでもらえるといいのかな」とも。読了後、彼女がどういう視点でそう言ったのか、解釈を広げていくのもまた楽しいだろう。
書くことは好きだった
羊飼いと作家というふたつの肩書を持つのは、日本では河﨑さんだけだろう。
「子どもの頃から本は割と好きでした。物語の続きを想像したりするうちに、自然と書いてみる側になってみたいとは思っていました。田舎だったので中学にも高校にも文芸部はなく、大学に入ってから文芸サークルに入って書き始めたのですが、早々に自分の才能のなさに嫌気がさしまして。今の自分には知識や人生経験が足りなくてたいしたものは書けないと思いまして、文芸サークルもやめてしまいました。マスコミ関係への就職活動もしましたが、一方で羊に興味が出てきて。学生時代に国産の羊肉を食べる機会があって、それがたいそう美味しかったのですが、国産の羊肉を生産しているところが少なく、研究もまだまだ余地があると耳にしたんです」
そこから留学、緬羊飼育を始めたのは前述の通り。再び創作活動を始めたのは三十歳くらいの頃だという。
「そろそろ手をつけないと、このまま何も書かなさそうな気がしました。筆を休めている間も北海道の郷土史や開拓期の体験記は面白く読み続けていたので、そういったものがベースになりました」
たとえば『肉弾』に挿入される、豚が人間の乳飲み子を食べたというエピソードは実際にあったことだという。
「六花亭のイラストを描いた坂本直行さんの息子さんが幼少期の生活を書いた本があって、そこに十勝の集落でそういうことがあったと、さらっと書いてあるんです。当事者にとっては大ごとだったでしょうから、それを物語として成り立たせてみました。そうした体験記や、おじいちゃんが孫に話すような話というのは埋もれてしまいやすい。物語として脚色なり拡大なりはしますけれども、こういう形で残しておきたい気持ちがあります」
好きな作家は、中島敦、そして古川日出男。古川さんの浸透圧のある文章が好きで、最初に揺さぶられた作品は『沈黙』だという。映画からの影響も受けており、パトリス・ルコントの「なぜここで沈黙のシーンを入れるのか、なぜここでこんなカットを入れるのか。間の分からなさがいちいち引っかかるところが楽しい」。
今はまた別の長篇に挑戦中だ。
「北海道を舞台にして書きたいものもたくさんありますが、長期的には、他のものにも挑戦していきたいです」