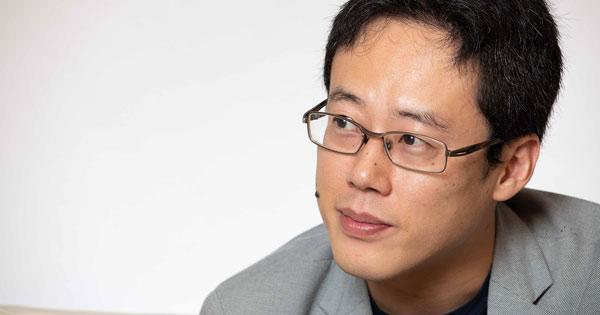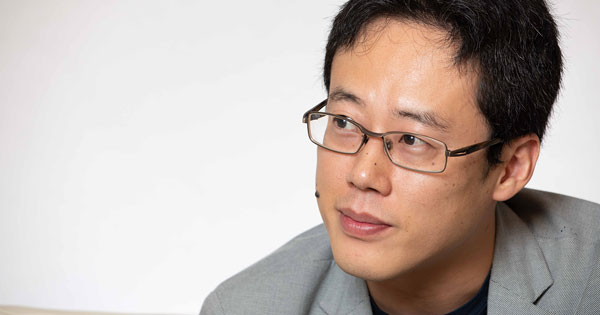私の本 第3回 白井 聡さん ▶︎▷01
連載「私の本」は、あらゆるジャンルでご活躍されている方々に、「この本のおかげで、いまの私がある」をテーマにお話を伺います。
戦後も続く「国体」という国家観。今年4月に『国体論 菊と星条旗』を上梓された、政治学者の白井聡さんに、まずは戦後の国体と、 それが現代に与えている影響について、詳しく教えていただきました。
支配の事実の否認
私の近著『国体論 菊と星条旗』は、明治維新から現在に至るまでの近現代史を「国体」という視点を通して論じたものです。
戦前の国体とは、「万世一系」の天皇が家長で、臣民はその子供であるという共同体の形を指したものです。
言ってみれば、天皇という大いなる家長のもと、国民全員が家族のように、自然に仲良く暮らしているという状態です。
そんな国家観は、一般的には敗戦を機に崩壊したことになっていますが、実際には戦後も続いていると私は考えています。
では、戦後の国体とはなにか。それはアメリカを頂点とするものです。戦前の天皇の存在が、戦後はそのままアメリカにすり替わったのです。
天皇の戦争責任論争の空転
その起源を見てみましょう。GHQは日本を円滑に統治するために、象徴天皇として天皇制を存続させることを決めました。
そこに関係するのが昭和天皇の戦争責任問題であり、さまざまに論じられてきました。保守派は「責任なし」と主張し、革新派は「責任あり」と主張してきました。
しかし、そこで見過ごされているのは、日本人が主体的に昭和天皇の戦争責任を問える立場にはなかった、という事実です。
そもそも、責任の有無を決めることができたのはアメリカであり、日本ではありません。
アメリカが政治的に「天皇には責任がない」と決めたのだから、天皇に責任はないとされました。
このストーリーに従って、昭和天皇が戦争を止めようとしたという発言ばかりがクローズ・アップされてきました。
これに対して、有責性を立証しようとする人々は、戦争を後押しした発言の存在を強調してきました。
しかし、もしアメリカが天皇に戦争責任を負わせるという反対の判断をしていたら、昭和天皇の好戦的な発言のみが注目されたことでしょう。
いままで、このことを想定しないまま右派も左派も、昭和天皇に戦争責任があるかないかを延々と論じてきました。
でも、日本はそもそも天皇責任があるかどうか判断できる立場になかった、敗戦の結果として判断する権利を奪われていた、そこまで惨めな敗北を喫したのだということを見落としているのです。

現代の閉塞感は、「国体」と関係がある
天皇責任を不問にして、天皇制を存続させることは、日本人を研究し尽くしたアメリカが下した決断でした。
このことが大きな要因となって、戦後の日本人は、自国が究極的にはアメリカに支配されているという事実を自覚しないままここまで来たのです。
支配されている自覚がなければ、自由になりたいという欲求も生まれません。被支配の状態にあること、つまりは不自由を自覚するところから、自由への希求が始まるからです。
そして自由への希求がなければ、知性も生まれようがありません。何とか少しでも自由になりたいと思うからこそ、知恵も生まれるからです。
その結果、いまの日本には反知性主義と自由の自発的放棄、ならびに自発的な自由の抑圧といった深刻な現象が現れています。
そもそも、西洋近代的な人間像とそれに基づく国家と社会の理念と国体概念に基づく家族国家観は大変相性が悪い。
西洋近代の世界観によれば、人間はエゴイズムの塊であり、そのために衝突も起こると想定されています。だからこそ、衝突を調停するものとして「権利」の概念が重要にもなるわけです。
しかし、国体概念に由来する家族国家観は、まさにそうした人間のエゴイズムの対立・衝突・闘争という現実を否認します。
法体系をはじめとして戦後の社会制度は、西洋近代的な人間像に依拠しているにもかかわらず、国体的な国家・社会像が生き延びているわけで、そこに摩擦が生じるのです。
たとえば、誰かが不当に不利益を蒙る出来事が起きたときに、「おかしいのではないか」と声を上げる人間に対して「黙れ」「それはお前のわがままだ」といって抑圧するのです。
それはSNSなどが発達した現代においては、極めて重大な社会問題となっています。イナゴの大群のようにいっせいに批難を浴びせかけて、集中砲火するという醜悪きわまる行為が横行しているわけですが、そんな社会に閉塞感が漂うのは当然です。
全員が無権利状態に置かれている社会で「権利付与」や「権利回復」を唱える人間は、不当な特権を要求しているように見えてしまうのです。
かくして奴隷根性が蔓延(はびこ)り、国際関係における従属構造は、国際関係の次元にとどまらず、日本国内の社会を腐食させるに至りました。

アメリカに自ら従属する日本人
それでも70年代前半頃までは、日本中に米軍が駐留していることに対する拒絶反応というのはありました。
その感情が爆発した最大の出来事は60年安保闘争でしたが、その後、日米同盟の恩恵により日本が高度経済成長へと突入し、やがて経済大国となったわけです。
経済大国であることを享受した日本には、同盟関係を壊してまで独立することにリアリティーがなくなってしまいます。
同時に、アメリカによる支配の構造が、不可視化され、人々に自覚されない形で存続することになりました。
本来なら、日米安保を基軸とする対米従属は東西対立があってこそのことだったのですから、冷戦が終わったときに独立についての議論が再び起きてもおかしくなかったのです。
しかし、アメリカに支配されていることすらもはやわからない日本人には、そこから脱しようという発想も浮かばなかった。
そうやって長い時間をかけて、日本は自ら主権を放棄し、アメリカに従属していったのです。
もちろん、どんな主権国家であろうと、孤立した形で存続することはできません。しかし、ここまで従属を自己目的化させて自発的にアメリカについていく国というのは、他に類がありません。
つづきはこちらからお読みいただけます
白井 聡さん ▶︎▷02