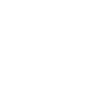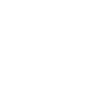“後天的家族”を描く連作短篇集
2013年にすばる文学賞を受賞した『左目に映る星』(「アナザープラネット」を改題)、第二作『透明人間は204号室の夢を見る』がともに話題を呼んだ奥田亜希子さん。
「中学生の頃にライトノベルのようなものは書きましたが、今に繋がるような小説を書き始めたのは社会人一年目で会社を辞め、結婚してからになります。最初に書いた作品が新人賞の一次だったか二次だったかを通過したので、それで道を誤ったというか(笑)。そこから六年、応募生活を送っていました。最初の投稿で一次落ちしていたら、今はもう書いていなかったかもしれませんね」
応募当時は純文学かエンタメかといった分野を意識することはなかったという。
「本当に分かっていなくて、完成したものの枚数と応募締め切りで応募先を決めていました。だから最初に応募したのは確か『小説宝石』で、その一次を通過したものを手直しして『群像』に送ったら二次を通過した、なんてこともありました」
待望の第三作は短篇集『ファミリー・レス』。テーマは“後天的家族”だという。耳慣れない言葉である。
「『左目に映る星』の単行本を出したすぐ後くらいにKADOKAWAの編集者さんとお会いして、これまでにどんなものを書いてきたかと訊かれて恋愛か家族をテーマにしたものが多かった、と答えたんです。それもあって、その後『小説野性時代』で家族特集が組まれる時に短篇の依頼をいただきました。その時期にいちばん興味があったのが、生まれ育った家族よりも義理の家族でした。ちょうど自分が結婚して、家族というものの意味が変わっていった時期だったんです」
もともと家族ものを書いていたというのも、人が生活していくなかでの感情に興味があったからだと思う、と奥田さん。そこから単行本では二篇目に収録されている「指と筆が結ぶもの」が生まれた。主人公は売れない画家の鉄平。妻の万悠子は広告代理店勤務で、経済的には彼女が頼りだ。そんな万悠子側の親戚の地方での結婚式に出席したため、夫婦は彼女の祖父母の家に泊まることに。鉄平にとっては決して居心地がいいわけではないが、ひょんなことから、十三年前に失明したおじいさんと心を通わせる瞬間が訪れる。
「以前、絵を描く友人が、表現するものに自分の本質が出る気がすると言っていて、そこから絵を描く人と目が見えない人は分かりあえるか、ということを考えたことがあって。文章などの表現だったら目が見えなくても通じ合えるけれど、絵は難しいのかもしれない。それで、絵を描く人と目が見えない人の話を書いてみようと思っていたんです。錯覚であっても大事なところが通じ合った、とお互いに思えたらいいんじゃないか、ということが言いたくて。それがなぜ仕事のない夫と代理店の妻という組み合わせになったのかは分かりません。ただそれも、本人たちがいいならそれでいいじゃないか、という気持ちが根底にあったんだと思います」
この短篇を雑誌に掲載後、連作にして本にまとめるという話になった。
「それで、いわゆるストレートな家族ものではない話を書いて一冊にまとめられたら、という話になりました。“後天的家族”という言葉ははじめての打ち合わせの時にすっと出てきた私の造語です。あとでインターネットで検索しても引っかからなかったので、この言葉を使っても大丈夫だなと思って。生まれ育った時から一緒だった、先天的な家族ではない家族という意味あいです」

さまざまな人と人との家族的繋がり
巻頭におかれたのは「プレパラートの瞬き」。広告代理店の新入社員、希恵は実家を出て女性限定のシェアハウスで暮らし始める。母の影響で、姉とともに人の悪口や愚痴を言えない性格となった彼女は、時に場を白けさせてしまっている様子。一方、同居人で町工場の事務をしている葉月さんはかなりの毒舌家。正反対の二人だけれども気が合うようで、ある時希恵は、葉月さんの毒舌によって救われる。
「前向きな性格が、親の教育によるものだったらどうだろうと考えました。というのも今、自分が子育てをしていると、これって洗脳みたいだなと感じることがあるんです」
人の悪口を言うと罪悪感を抱くというご自身の性質も、親の教育によるものではないか、と思い至ったという。
「私の友人も、みんな人に無神経な態度をとれない人が多いんですが、そういう風に育てられてきた結果だろうと感じるんです。でもその一方で、矛盾するようですが学生時代にすごく毒舌家の友達がいたんですよ。本人も人からよく見られようとは思っていなくて、悪口を言っていると自覚している。それで、“あー、人の悪口言うのって面白い”と言う(笑)。そういう様子を見ていて、自覚のない悪口はよくないけれど、最低限のマナーさえ守れば、人を悪く言うことで救われる人もいるんじゃないかなと感じました」
三話目は「ウーパールーパーは笑わない」。再婚した元妻と暮らす娘とはたまに会うものの、無神経な物言いで傷つけてしまう父親。彼は気まぐれにウーパールーパーを飼い始める。
「離婚して一緒に暮らしていない父親と娘という家族の形を書くと同時に、娘にとっては義理のお父さんが後天的家族なので、それを少し遠いところから見つめてみたかった。主人公にとってはウーパールーパーも後天的家族ですよね。成長しない駄目な男の人を書こうとは決めていたんですが、この話がいちばん、好きになってくれる読者がいるかどうかが不安で……」
と著者は言うが、ダメ男が自分のダメさに気付く場面は哀れだが痛快でもあり、今後の成長の予感に希望も感じさせる。

主人公は少年から犬まで
「さよなら、エバーグリーン」は少年が主人公。短期間だけ家に滞在することになった曾祖母との交流と同時に、小学生から中学生に成長するにつれ変わっていく教室内の優劣関係や、淡い初恋の行方が丁寧に描かれる。
「血は繋がっているけれども、すごく遠いところにいる存在と通じ合う瞬間を書きました。小中学生の頃の恋心についても書きたかったですね。大人になると関わり合いのなかで、相手が自分を気に入っているなと感じて告白したりする。でも小中学生の頃って、自分から遠い存在の人に思いをはせることがありますよね。この頃の恋愛だけが本当の恋愛だという気もします。あの100%純粋に好きになっている感じが書きたかったのかもしれません」
次の「いちでもなく、さんでもなくて」は事故死した双子の姉夫婦の一人娘を引き取った妹とその夫の話。本当の娘のように育てた姪が一人前になり、家を出ると宣言されてショックを受ける主人公だったが……。
「双子ってすごく不思議な存在ですよね。亡くなった双子の姉の娘となると、半分は自分の遺伝子になるわけですよね。その感情の行きつく先はどうなるのかが気になりました。実際に双子の子たちに会う機会がありますが、お母さんはちゃんと見分けられるのがすごいなと思うし、自分がもしも双子だったら、見分けてもらえるのって嬉しいだろうなとも思います。そうしたことが組み合わさってできた一篇です」
最後の「アオシは世界を選べない」はなんと、後天的家族の一員である飼い犬が語り手だ。父親を亡くしたばかりの片江家に、故人に線香をあげるために一人の青年が訪ねてくる。出迎えたのは事情があって実家に戻ってきている長女の亜砂と飼い犬のアオシ。人間二人は初対面のようだが、アオシはその青年を知っている様子。もちろん亜砂はそのことに気付かず、二人のやりとりはいつしか意外な展開をみせ、驚きの事実も明らかに。二転三転する会話で楽しませるシチュエーションコメディのよう。
「一篇は犬の視点で書くというのは最初から決めていました。でもいざやってみたら難しかったですね。犬がどこまで分かっているか気をつけなくてはいけないし、色は識別できないだろうから一切描写しないようにしたりして。いつも会話が続く原稿を書くと枚数を稼いでいるようで気になって苦手だったので、会話文を鍛えたいという気持ちもありました」
犬が主人公と分かれば、タイトルの「世界を選べない」は「家族を選べない」と同じ意味だということも分かる。
「この話を書いた頃には書きたいことがはっきり分かっていました。人にとって後天的家族は選べるもの。だからこそ、選んだことも選べなかったことも意味を持つ。そういうことを強く感じながら書きました」

完成度の高い一篇一篇になったのは
家族だから言えないこと、他人だから言えることがあるように、人と人は近いからこそ遠くに感じることもあれば、遠いからこそ近しく思える時もある。そのなかで生まれる奇跡のような触れ合いや繋がりを、さまざまな読み心地で読ませる本作。「プレパラートの瞬き」の希恵が「指と筆が結ぶもの」の万悠子の会社の部下である、というように登場人物同士が緩やかな繋がりを持っているが、満足度を高めるのは短篇同士で内容を補完しあうことなく一篇一篇が濃度の高い、独立した作品として完成されている点だ。これは自身も心掛けたという。
「いつも百枚から二百枚くらいのものを書いていたので、五十枚くらいの短篇というのは私にとって未知の荒野で、どういうふうに書こうか考えました。もともと連作短篇集は好きでいろいろ読んでいましたし、ひとつの短篇がもうひとつの短篇の種明かしみたいになるような連作も小説だからこそできることだなとは思うんです。でも、それだとそこで世界が閉じてしまうような気がしてしまって」
たとえば主要人物が二人登場する短篇があるとして、一篇を片方からの視点、もう一篇を相手側からの視点で描けば、双方向から世界が浮かび上がるものの、そこからの広がりはない。
「同じ人物を登場させるにしても、ほんの脇役だった人が次の話の主人公になるような書き方ならば、どんどん世界が広がっていって、遠くに行けると思いました。飽きやすくてくどいことが苦手なので、同じことを何度も書くのが嫌だ、ということもありますね。さまざまなものが書きたかったんです」
どの話も、脇役に至るまで人物が丁寧に作られ、物語世界が立体的になっているのは、そんなふうに俯瞰する目を持っているからだろう。だからこそ、共通のテーマながらトーンもさまざまな、作者の力量を示す作品集となっている。
すばる文学賞でデビューとなると純文学のイメージも強いが、今回の作品でジャンルにとらわれずに書いていくのでは、という予感を一層強くさせた。
「私も角田光代さんや吉田修一さん、江國香織さんのように純文学もエンタメも書いてきた方の作品がとても好きです。実は私と同じ生まれ年の作家の方ってとても多いんですが、すごく文章が好きな方が多くて。島本理生さん、青山七恵さん、金原ひとみさん、深緑野分さん、加藤千恵さん、学年が一緒の綿矢りささん、芦沢央さん……」
確かに1983年とその前後の生まれの人気作家の多さに驚く。いい刺激を受けながら、奥田さんもその一人として活躍していくに違いない。現在は書き下ろしなどに取り組み中だという。
(文・取材/瀧井朝世) |