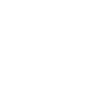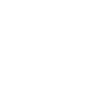今月飲むのを我慢して買った本
古書を収集する主人公がそれぞれ迎える結末に、薄ら寒くさせられる芦辺拓さんの連作短篇集『奇譚を売る店』。
中目黒ブックセンター(東京)佐藤亜希子さん 
お酒は好きではないです(などと言ったら周囲に鼻で笑い飛ばされるに違いありません)が、飲んだときのふわふわとした感覚は大好きです。そんな酩酊感をお酒を飲まずとも楽しめる素敵な本をご紹介いたします。
一冊目は長野まゆみさんの『45°』。一見するとありふれた日常を描いた短編集なのですが、どれもが奇妙なねじれかたをしています。隣りの席から聞こえてくるある事件についての会話とその顛末、電車内で見かけた小学生の名前から蘇る記憶、行方不明の義兄が語った不思議な体験談。登場するのはごく普通の人物たちなのに、どこか歪んだストーリーを読んでいると自分も奇怪な世界に紛れ込んでしまったかのような擬似体験が味わえます。そしてその居心地の悪い感覚は、いっそ呑み込まれたくなる魅力を携えていて、本を閉じたあとにまで続くのです。
二冊目はジョイス・キャロル・オーツの『とうもろこしの乙女、あるいは七つの悪夢』です。表題作は子供ゆえの残酷さと行き場のない感情が招いた少女誘拐事件にまつわる物語。登場人物たちの心理描写があまりにもリアルで、読んでいて胸が苦しくなってくるのに、おとぎ話のような儚げで美しい空気感が漂っています。嫉妬、憤怒、保身、依存、自己顕示欲、ここまで過剰ではないにしろ、自分にも身に覚えがある負の感情の連鎖から目を背けたくなりつつも、サスペンスめいた展開も手伝って、取り憑かれたように読み進めてしまう作品でした。
三冊目は芦辺拓さんの『奇譚を売る店』です。「─また買ってしまった」と収集癖がある方なら何度も呟いたことがあるであろう一言で全編が始まる連作短編集で、この物語の主人公は古書を収集しては、その本にまつわる怪奇めいた世界に引きずり込まれていきます。買い求めた本はミステリや年代記もの、病院の案内書もあれば関係者向けの映画パンフレットなどとジャンルはさまざま。主人公が迎える結末にはそれぞれ薄ら寒くさせられるのですが、最終話で今までは他人事だと感じていた恐怖が我が身に降りかかる、そんな逆転劇のようなオチが口をぽっかりと開けて待っています。あぁ、私もこんな世界に入り込みたいと願う反面、どうして自分が焦がれる世界はこんなにもおぞましいものばかりなのかと首を傾げながらウイスキーを飲む日々からは当分抜け出せそうにありません。

当店の売れ行き30位前後にいる小説
都市伝説の謎を暴く平山瑞穂さんの『マザー』は、今在るべきこの瞬間をまるで宝物のように育みたくなるお話。
ブックポート203中野島店(神奈川)渡辺美由希さん 
当店でずっと売れ続けている沼田まほかるさんの『彼女がその名を知らない鳥たち』は、かつて別れた昔の男を忘れられない女が嫌悪感しか抱けない別の男と生活を共にし、次第に事件に巻き込まれていくミステリー小説。
この作品を初めて読んだのは二年程前ですが、未だに題名を見るだけで涙が出そうになります。それだけ内容が強烈でした。
とはいえ、過激すぎる暴力シーンや血なまぐさい残酷な描写があるわけではなく、人間の内側に潜む汚さや醜さみたいなものが、見事に綺麗に描かれているという衝撃。
読んでいるうちにこれでもか〜!と人の心を抉ってくるのに、いつの間にかそれがとても純粋で美しいものに形を変えている不思議さ。暗闇に沈む月が実は無数の光を帯びた太陽だったような、奇跡のような感覚でした。とにかくラストは必見。一度読んだらもう手放すことのできない感動が待ち受けています。
次にご紹介するのは、平山瑞穂さんの『マザー』。
その人がいたという痕跡はあるのに、記億がいつの間にかなくなっている。そんな都市伝説の謎を暴くお話です。次々に起こる展開には終始目が離せず、読めば読むほど様々な人たちのせつなさや葛藤、苦しみなどが痛いほど伝わり今在るべきこの瞬間をまるで宝物のように大事に育みたくなるお話でした。
ミステリー、恋愛、青春、SF。様々な要素が入ったこの作品はたくさんの方たちが楽しめる万能小説といっても過言ではありません! ひとつひとつの出来事が心に響くこのお話は、是非たくさんの方たちに共感してほしい作品です。
最後に吉野万理子さんの『連れ猫』をご紹介します。普段から大の猫好きということもあり、思わず表紙買いしてしまったこの作品は、主に文中に登場する二匹の猫“ソリチュード”と“ロンリネス”の視点から物語が進んでいきます。
どちらも『孤独』という意味で名づけられたこの猫たちと、それに関わる人間たちを通して孤独とは何かを真摯に読み手に問いかけてくれます。
誰もが覚える色々な孤独の形。人は弱い。けれどそれを受け入れたときもっと強くなれるということをこの作品から教わりました。自分自身に立ち向かう勇気と希望をもらえる一冊です。

私はこの本を1日1冊1すすめ
瀬川深さんの『ゲノムの国の恋人』には、ゲノムから見れば「世界中どこでも同じ」という大きな愛がありました。
宮脇書店松本店(長野)月元健伍さん 
一冊目は第一四九回直木賞の候補にも入った、宮内悠介『ヨハネスブルグの天使たち』です。
内戦が激化した南アフリカの高層タワーでは、まるで「夕立」のように大量の少女が落下し続けていました。
実は少女たちは「歌姫」と呼ばれるホビーロボットで耐久試験のためにプログラムされた落下行為から逃れることができません。戦災孤児の少年少女がそのうちの一体を助けようとするところから表題作は始まります。
どの短篇も「歌姫」と、現代日本からすると非常にハードで読者の問題意識をくすぐるモチーフが出てきます。閉塞した近未来に胸を痛めながら読み進めると、そんな気分を一息に覆すとても人道的な、心揺さぶる感動が待ち受けます。暗い未来を描いていながら確かにいまに通じる普遍性が存在します。いまの閉塞感に対してどのように現実を拡張し生き抜いていくのか、その方法を提示してくれるすばらしい小説です。
二冊目は「ロシアの村上春樹」と呼ばれているヴィクトル・ペレーヴィン『宇宙飛行士オモン・ラー』です。冷戦下のソビエト、月探査のため打ち上げられた月面ヴィークル。その自動機械の動力源として自転車を漕ぎ、「プロの英雄」になるべく選抜された若者オモンの物語です。
二重三重の虚構性からソビエト人の内宇宙を描いていると言い切ってしまうのも簡単ですが、それは何もこの国に限った話ではないわけで─だからこそラストシーンが本当にぐっと来ます。
表紙を含め、装丁がすごくかっこいいのでずっと手元に置いておきたくなる小説です。
三冊目は瀬川深『ゲノムの国の恋人』です。押しは弱いけれど生真面目な理系研究者・タナカは将軍閣下の姫君選びのために怪しいアジアの独裁国家に招かれます。奇想天外な国に翻弄されるさまに手に汗握ったりクスクス笑ったりしていくうちに、タナカを始め七人の姫君や将軍閣下、ラワヤ兵長の魅力的な登場人物たちから目が離せなくなってしまいました。
その根底にはきっと、ゲノムから見れば「世界中どこでも同じ」という、大きな愛があるのだと思います。
まったく瀬川深の小説はとっても愛らしくてユニークですよ!
掲載の記事・写真・イラスト等のすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。
Shogakukan Inc. All rights reserved.
No reproduction or republication without written permission. |